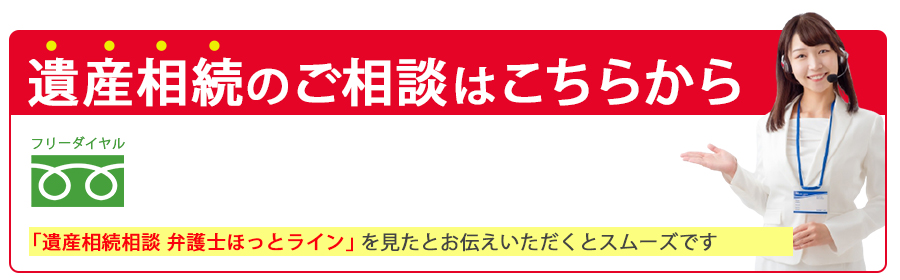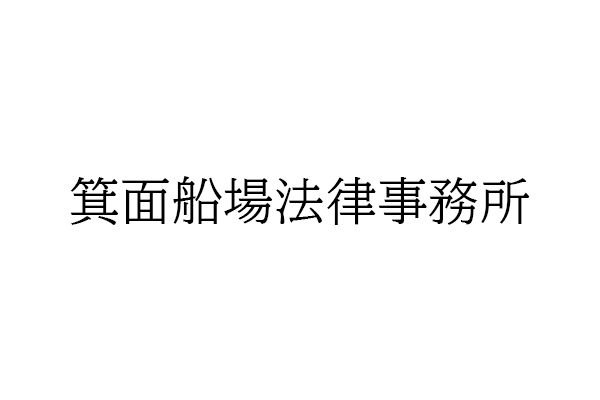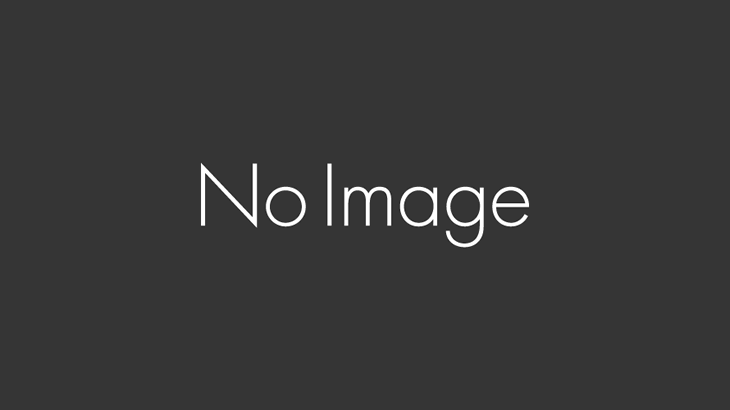箕面船場法律事務所

| 事務所名 | 箕面船場法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階 |
| 担当弁護士名 | 脇田 圭吾(わきた けいご) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.49238 |

箕面船場法律事務所の2つの強み
「地域に特化したサポート」と「専門家との密接な連携」が当事務所の特徴です。
箕面船場に特化した地域密着型
大阪・箕面市で当事務所を開業しました、弁護士の脇田 圭吾(わきた けいご)です。当事務所は箕面船場エリアの数少ない法律事務所であり、地域に根差した活動をモットーとしています。
当事務所は新御堂筋沿いに位置しており、お車でお越しやすい場所にあります。ご依頼をしていただいた方には、周辺のコインパーキングの駐車料金を当方で負担いたします。電車でいらっしゃる場合には、千里中央駅から最寄りのバス停である「新船場北橋」までバスでお越しください。バスは駅から10分間隔で運行しています。
不動産相続はローカルの弁護士へ
相続の中でも特に不動産の相続は、その土地の事情に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。ローカル事情を十分に理解しており、そのエリアでの取引データもあるためです。
現物で相続された不動産を代償分割(建物など分けられない財産を相続する際に、現物を相続する方が他の相続人に対して代償金を支払うこと)するケースや、不動産を売却して現金化してから相続するケースでは、その不動産に対して査定をして評価額を算出する必要があります。エリア事情に詳しい当事務所弁護士が、皆様が安心して相続できるようにお手伝いします。
土日祝日、平日夜間も対応
相続が発生した時に、手続きをどこから始めて良いか悩まれる方は少なくありません。被相続人の方が遺言書を作成していなかった場合はなおさらでしょう。
当事務所は土日祝日を含め24時間体制で円滑な解決を目指して尽力いたします。
各分野のスペシャリストと共にトータルサポート
税理士と連携して相続税の負担軽減の対策ができる点も当事務所の強みです。相続税は遺産をどのように分けるかで、時には何倍にも変わってきます。
また、司法書士とも連携しているため効率の良い手続きが可能です。相続登記は戸籍などの書類の取得など様々な準備が必要ですが、当事務所ではワンストップで対応が可能です。
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前にご予約いただきましたら土日祝、時間外でのご相談も可能です。 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 北千里駅 |
| 対応エリア | 大阪府 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
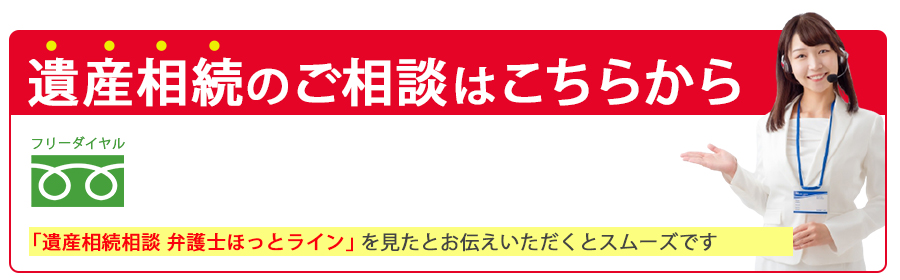
【対応分野】箕面船場法律事務所
これらのお悩み、一緒に解決します
相続は様々な法律が関与していて、よく分からないと感じている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、各法律は皆様の身近なお悩みに関わっていることもあります。以下のようなお困りごとを抱えている場合、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
もらえるはずの「遺留分」…今さら請求できる?
被相続人の配偶者や直系卑属(子どもや孫など)のような法定相続人には最低限の遺産(遺留分)が相続される保障があります。
被相続人が生前に遺言書を作成しており、特定の相続人に全てを贈ったケースなどでも適用されます。
例えば、あなたも法定相続人であるにも拘わらず、亡くなった親があなたの兄弟など誰か1人に全財産を相続させていた場合などには、遺留分を取り戻すことができる可能性があります。
遺留分を取り戻す時効は1年
このように遺留分を侵害された場合には、相続人は遺留分侵害額請求をすることが可能です。遺留分は遺言書よりも効力を持っています。
ただしこの請求は「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に行う必要があります。時効を過ぎてしまったら遡って請求することはできません。期限が短いため、もしかして…と感じたらお早めにご相談ください。
遺留分を請求する立場の方からだけではなく、請求される側の方からも、請求の内容が正しいのか分からないというご相談をいただくことがあります。当事者双方が納得できるように状況を整理しましょう。
見えない贈与、どう扱う?
「特別受益」や「寄与分」といった隠れた贈与が、相続の際にトラブルを生じさせるケースも頻繁に見受けられます。
生前に受けた利益は隠れた相続
被相続人が亡くなる前に相続人が何らかの財産をすでに贈与されていた場合、それを「特別受益」といいます。
複数人で相続を分割する際には、それぞれの相続人の特別受益を加味して相続分を決めることで不公平を是正することが可能です。そのため特別受益は相続で重要な役割を果たすといえます。
ここでトラブルになりやすいのは、何を特別受益とみなすかについてです。
結納金や結婚式の費用などは扶養義務の一環と捉えられ、これに該当しないと考えられます。一方で、会社設立のための資金や成人した子に対する生活費用の援助などは特別受益と判断されることが多くあります。
ただし、大学の学費は義務教育ではないものの扶養範囲と捉えることもでき、その家庭の収入や環境によって判断が分かれるポイントです。
介護したのに、他の兄弟と相続分が同じ…
親と同居していた方の中には、生前に介護をして貢献したにも関わらず、他の兄弟姉妹と同じ相続分であることに納得がいっていない方もいるかもしれません。
介護のように、被相続人に対して行った生前の特別な貢献を「寄与分」といいます。これが認められれば、その分だけ他の相続人よりも多く相続をすることができます。
注意すべき点は、寄与分が認められるには高いハードルをクリアしなければならないということです。親子の関係において子が親の老後の介護を担うことは法律上当然であるとみなされます。よって、寄与分を主張するためには通常期待される以上の貢献をしたことを証明する必要があります。
寄与分に関するトラブルはお互いが感情的な側面で対立することが多く、当事者のみでは合意の道筋をなかなか見出しにくいです。弁護士などの第三者を含めた話し合いが円滑な解決への近道です。
相続トラブルを未然に防ぐために
ここまで、相続が発生した際に争議になりやすいポイントを紹介してきました。
大切なのは、トラブルにならないように前もって準備しておくことです。「遺言書」や「生前贈与」を活用して遺産分割の内容を事前に示しておくことで、もしもの場合にあなたの配偶者や子供の負担を軽減することに繋がります。
遺言書は公正証書遺言で残すべき
遺言書には3つの種類があります。
「自筆証書遺言」
遺言者が全文を手書きで記し、押印をしたものです。遺言者が1人で作成することができますが、紛失や改ざんの恐れがあることや相続人自体が遺言書の存在に気づきにくいことが挙げられます。
「秘密証書遺言」
遺言者が署名・押印したものを封印し、さらに証人など複数人で署名・押印して作成します。改ざんの危険性が低いことに加え、遺言の内容を他者に知られることがない点がメリットですが、手続きが複雑かつ形式不備で遺言が無効になるリスクがあります。
「公正証書遺言」
遺言者が口授した内容を、公証人と呼ばれる法律の専門家が証人の立会いの下で記して作成するものです。公証人が責任を持って筆記・訂正の手続きを行うため、形式不備による失効を防ぐことができます。また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、破棄されたり書き換えられたりしてしまう心配もありません。
以上をふまえると、遺言は「公正証書遺言」で残すのが望ましいでしょう。
「生前贈与」は事後トラブルになりやすい
遺言書の作成とは別に、相続トラブル対策として「生前贈与」を検討する方も増えています。
「家族や子供が自分の遺産相続で揉めないように」と考えて財産を移転したものの、残念ながらこれが後々問題を引き起こしてしまうケースもあります。
生前贈与を行う前に、それが特別受益に当たるかどうかを注意して考えなければなりません。該当する場合は、生前贈与を受けた相続人はすでに遺産の一部を譲り受けているとみなされ、相続発生時に期待していた相続分がもらえない可能性があります。
生前贈与を行う場合には、将来どのように財産を相続させるのかを見据えて、長期的な視点から進めていく必要があります。ご検討されている場合は、贈与をする前にぜひ一度ご相談ください。
第三者の介入で親族間の関係性にしこりの残らない解決を
遺産相続は親族間の紛争になることが多く、当事者同士で折り合いをつけることが難しいものです。
話し合いが進まずに膠着したまま長い年月が経ってしまうと、これがきっかけで親族の関係性に軋轢が生じてしまう恐れもあります。これでは財産を残した被相続人にとっても不本意です。そのような深刻な問題にならないよう、当事務所がご依頼者様の最大の味方となってスムーズな円満解決へと導きます。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。