藏王法律事務所

| 事務所名 | 藏王法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-2410 |
| 所在地 | 〒153-0053 東京都目黒区五本木1-35-7 SKMビル2階 |
| 担当弁護士名 | 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.62773 |

銀行勤務を経て弁護士へ
私は、大学卒業後、大手都市銀行に勤務して、主に法人及び個人に対する融資業務に従事しておりました。したがいまして、銀行業務を通じて、相続財産に含まれていることの多い預金、投資信託や株式といった金融資産に知見を得ることができました。また、融資をする場合、不動産や株式を担保に取ることもあり、その際にはこれらの資産の評価をすることもありました。
そして、相続においても不動産や株式といった資産の評価が必要になることがありますので、弁護士になってから相続事件を取り扱う上で、銀行での経験は大いに役立っておりますし、そのことが、私が相続事件に力を入れている理由の1つです。
さらに、銀行の融資担当という仕事柄、法人・個人を問わず、事業を営んでいる方とも数多くお話をさせていただきましたので、事業を営んでいる方の事業承継のご相談にも対応できると考えております。
| 定休日 | 土・日・祝 | |||||||||||||||
| 相談料 | 30分 5,500円(税込) | |||||||||||||||
| 最寄駅 | 祐天寺駅(東急東横線)より徒歩3分 | |||||||||||||||
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | |||||||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 メールでのお問い合わせは365日24時間受け付けております。 |
|||||||||||||||
| 着手金 | ※下記料金は目安です。ご相談後にお見積りをいたします。
|
|||||||||||||||
| 報酬金 |
|
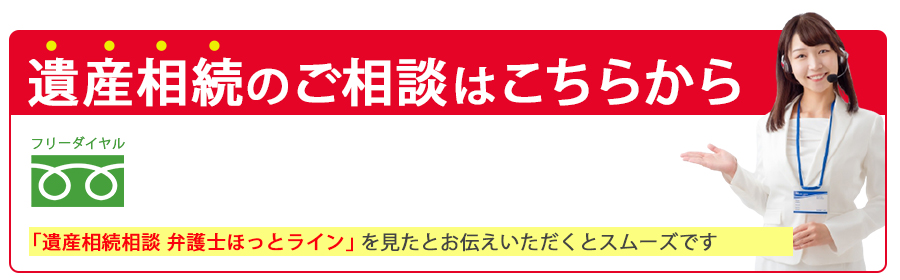
【対応分野】藏王法律事務所
相続分野において弁護士に期待されているのは紛争の解決
現在、相続分野には多くの職種の方が関わっておりますが、依頼者の方あるいは社会が弁護士に最も期待しているのは、相続で実際に紛争が生じてしまった場合の解決だと思います。
弁護士は、高度な法的知識を有しており、また、裁判例や審判例にも通暁しており、裁判所を利用した手続きも熟知しておりますから、相続における紛争解決は弁護士の仕事です。
相続紛争にオーダーメイド対応
相続における紛争は、遺言関係、遺産分割関係等、後で述べるように一定の類型化はされておりますが、実際に個々の事案に接するとその内容は実に様々で1つとして同じものはありません。紛争に至ってしまった経緯、被相続人と相続人の関係、相続人間の関係、遺産の状況、依頼者の希望や相手方の対応など個々の事案ごとに異なりますし、その解決方法も事案ごとに異なります。
また、依頼者の方の故人や相手方に対する感情が複雑な場合もありますし、さらに相続紛争は人生の中で何度も経験するものではありませんから、依頼者のなかには相続が紛争に至ってしまったことに精神的な負担を感じていらっしゃる方もいらっしゃいます。
私は、こうした依頼者の方の感情や精神的な負担に配慮しつつ、依頼者の方と一緒に考えながら依頼者の方にとってベストな提案することを心がけています。各依頼者の方の個別の事情に応じた、いわばオーダーメイド対応をすることが重要だと考えています。
裁判例や審判例の調査分析を重視する
弁護士であれば当然といえばそれまでなのですが、私は裁判例や審判例の調査分析を非常に重視しています。と申しますのも、裁判例や審判例の徹底的な調査分析は依頼者の利益に直結していると思うからです。
まず、裁判所や審判例の調査分析によって訴訟や審判の見通しをつけることができます。もちろん、どちらに転ぶか分からないような見通しがつけにくい案件もありますが、一定の見通しがつけられる場合もあります。一定の見通しをつけた上で、何が依頼者の方にとって最適の解決策かを一緒に考えていきます。
例えば勝訴の見込みが低いのに訴訟を提起することは依頼者の利益に反することが多いでしょうし、認められる可能性の低い事実上・法律上の主張は証拠収集等に無駄な時間や労力、費用を費やすことになり、これもまた依頼者の利益に反します。逆に、勝訴や依頼者の方の主張が認められる可能性が一定程度あり、依頼者の方が望むのであれば、事案に応じた適切な手続きを選択して、依頼者の方の利益確保に全力を尽くします。
次に、裁判例や審判例の調査分析によって、裁判所がどのような要素を重視して判断しているのかが分かりますし、訴訟や審判等での主張立証のポイントを把握でき、どのような主張が説得的なのか、また、それを基礎づけるためにどのような証拠が必要なのかが見えてきます。そのことが、依頼者の方の利益の確保につながるのです。なお、必要な証拠やその収集方法についても適宜アドバイスしてまいりますのでご安心ください。
よくある紛争類型
相続紛争はいくつかの類型に分けることができますが、よくある紛争類型であり、私もその解決に力を入れているものについて簡単に述べます。
遺言をめぐる紛争
故人の遺言があった場合に生じる紛争の典型は遺言の有効性に関するものです。遺言があった場合、遺産はその遺言どおりに相続されるのが原則です。ただ、「遺言の内容が特定の相続人だけを優遇している。」、「故人がこのような遺言を書くとは考えにくい。」、「遺言が書かれた状況に不審な点がある。」といった事情がある場合に遺言の有効性が争われることがあります。
特に高齢化社会が進行している現在の状況では、認知症の方による遺言が、真にその方の意思に基づくものなのかが問題となることが多いです。こうした場合、裁判所は、遺言当時の認知症の進行の程度といった医学的見地と、遺言に至る経緯や遺言内容等から推測される遺言者の意思から遺言の有効性を判断しています。故人の意思というものは究極的には故人にしか分からないと思いますが、その意思を故人に聞けない以上残された者で故人の意思を探求していくことになります。
また、遺言の有効性が争われる場合、それが有効と判断されても遺留分の問題が残ることもありますし、無効と判断された場合にもやはり遺産分割の問題が残りますので、最終的な解決まで長期間を要することが多いです。したがいまして、遺言無効の主張を検討する場合、特に訴訟を提起する際には、事前に収集可能な証拠を収集するとともに、依頼者の方としっかりと話し合う必要があると考えています。
遺留分をめぐる紛争
遺留分とは、法律上、一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことです。その最低限の取り分が確保されていない場合には、遺贈や生前贈与を受けた者に対して最低限の取り分に至るまで金銭を支払うように請求できます。遺留分やその侵害額は計算がやや複雑ですから、この紛争類型は技術的な側面も有しております。
また、遺留分侵害額請求権は消滅時効にかかり、その期間も1年と短いです。したがいまして、自分に遺留分があるのではないかと考えておられる方は、専門家である弁護士にできる限り早くご相談されることをお勧めします。
遺産分割における特別受益や寄与分の主張
遺言がなかった場合、相続人間で遺産分割を行うことになります。遺産分割では自己の正当な取り分を確保することが大切です。遺産分割は法定相続分による分割がベースとなりますが、個別の事情によっては、それでは納得できないという場合もあるでしょう。遺産分割でしばしば問題になるのが特別受益と寄与分です。これらが認められるか否かで自己の取り分が大きく増減することがありますので重要です。
特別受益とは、遺贈や生計の資本としての生前贈与など一部の相続人のみが被相続人から受けた利益のことです。例えば、「弟は生前自宅の建築資金を出してもらっていた。」、「姉は先に亡くなった父親の相続の際に、母親から相続分の譲渡を受けていたから得をしている。」といった事情がある場合に特別受益が問題となります。特別受益においては、そもそも問題となった贈与が特別受益にあたるかや、特別受益にあたるとしても被相続人による持戻し免除の意思表示があったかなどが争点になります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持増加に特別の貢献をした相続人に与えられる遺産の取り分のことです。例えば、「長年にわたり母親の介護をしてきた。」、「父親の家業をずっと無給で手伝ってきた。」、「親が所有しているアパートを管理してきた。」といった事情がある場合に寄与分が問題となります。寄与分では、ある相続人の行為についてそもその寄与分が認められるかや、その具体的な金額または遺産に対する割合が争点になることが多いです。なお、寄与分は相続人にしか認められませんが、民法改正によって子の配偶者や孫などの相続人以外の親族が被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合に、それらの者が相続人に対して金銭請求できる、特別寄与料という制度ができました。
その他の相続に関する紛争や税務に関する問題なども一挙に解決
その他に、使途不明金の問題、養子縁組無効などの身分関係をめぐる紛争、祭祀承継や葬儀費用に関する紛争や遺産の管理に関する紛争など幅広く取り扱っております。
また、相続問題では、法的な側面のみならず税務的な対応が必要となることが多いですが、税理士と緊密に連携しておりますので、法務と税務の両面から最適な解決を目指すことが可能です。
事業承継
事業を営まれている方の事業承継についても取り扱っております。これまで蓄積された技術やノウハウ、取引関係を承継させることは後継者にとっても重要ですし、もう少し大きな視点からみればこれらを次世代に繋げていくことは日本社会全体にとって重要な課題だと考えております。
そして、事業承継後に安定的な経営を行うためには後継者に経営権を掌握させる必要があります。例えば、株式会社の場合には株式を後継者に集中させなければなりません。株式集中の方法としては、売買、生前贈与や遺言などの方法がありますが、それぞれメリットやデメリットがありますので、会社の現状や、現経営者の方や後継者の方のご希望を丁寧にお聞きした上で最適の方法を選択できるようにお手伝いいたします。また、株式の集中化の過程で名義株主や所在不明株主の問題が顕在化してくることもありますが、調査、交渉や売渡請求などの方法によってこれらの問題も適切に処理します。
さらに、生前贈与や遺言によって株式を承継させる場合には遺留分対策も必要になってきます。例えば、遺言によって株式や事業用資産を後継者に相続させたとしても、兄弟姉妹を除く他の相続人には最低限の取り分である遺留分があります。この遺留分を侵害してしまうと、結果として株式や事業用資産を後継者に集中させることができなくなって、後継者は安定した経営ができなくなってしまう可能性が出てきてしまいます。そこで、遺言書の内容を工夫したり、遺留分の放棄や経営承継円滑化法の特例を利用したり(除外合意、固定合意)、生命保険金を利用することなどによって円滑な事業承継の実現を目指します。
最後に
重複しますが、相続は人生の中で何度も経験するものではありませんし、初めて経験する方も多いと思います。また、自ら働いて得られるよりもはるかに大きな財産が相続によって手に入ることもよくあることで、相続紛争をどのように解決するかは依頼者の方の今後の人生設計に大きな影響を与えうるものです。
したがって、私としても、依頼者の方としっかりとコミュニケーションをとりながら、依頼者の方が納得できるような相続を実現できるように全力でお手伝いさせていただきたいと考えております。相続に関して少しでもお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
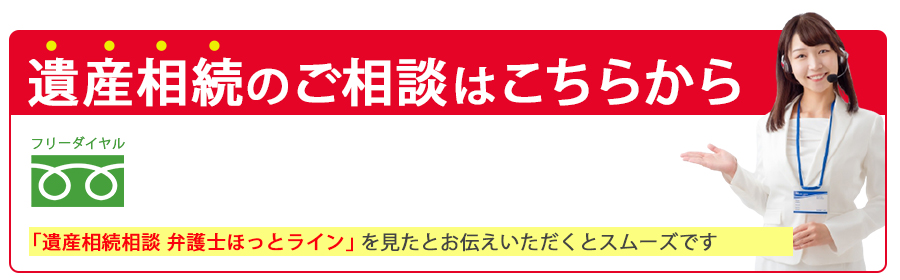
-
登録カテゴリや関連都市:
- 東京都

