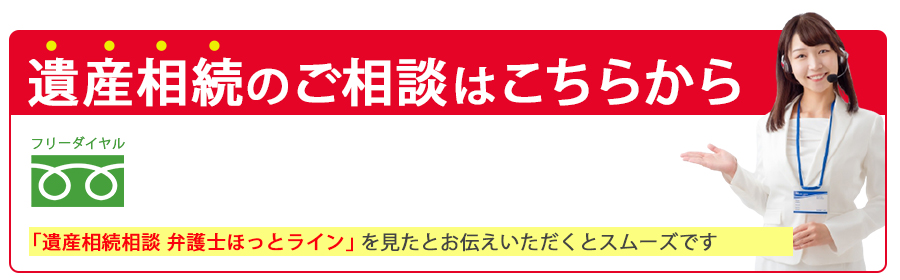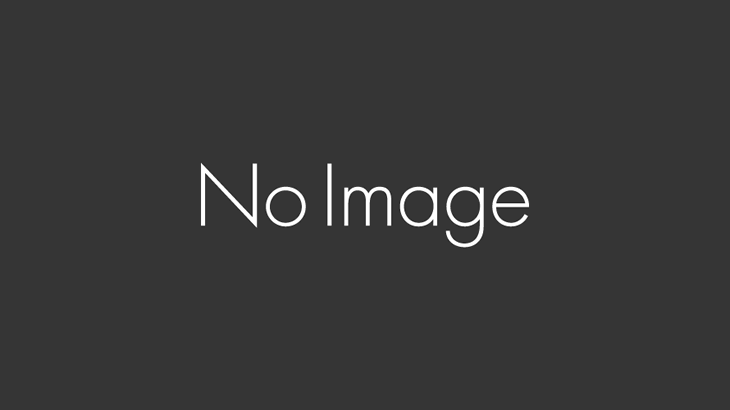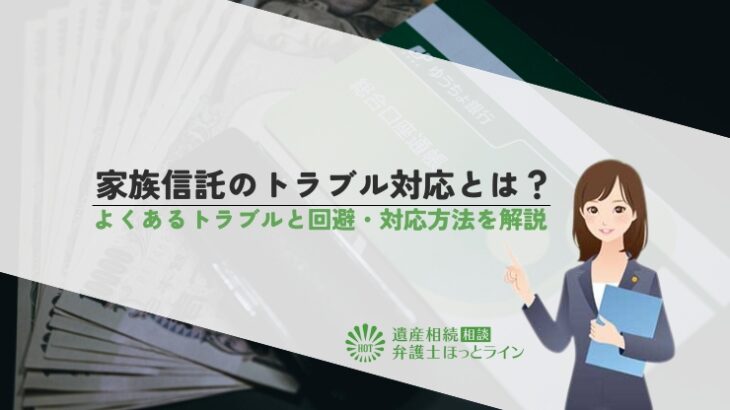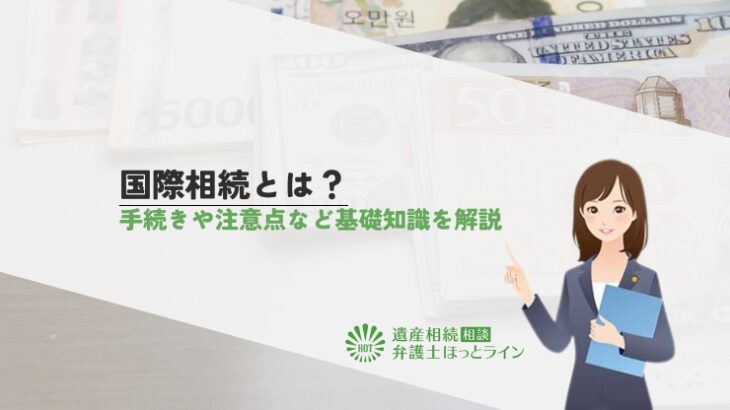ときわパートナーズ法律事務所

| 事務所名 | ときわパートナーズ法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル806 |
| 担当弁護士名 | 堀田 耕平(ほった こうへい) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
第一東京弁護士会 No.62434 |

相続・事業承継の悩み、まずはご相談ください
ときわパートナーズ法律事務所の弁護士、堀田耕平(ほった こうへい)と申します。長年、一般企業に勤務してまいりましたが、人生の後半は「人の役に立つ仕事に直接携わりたい」との思いから、弁護士の道を選びました。
相続には、不動産に関する問題が絡むことが多く、また自営業者の方にとっては事業承継が大きな課題となることもあります。私は会社員時代に培った不動産や企業法務の知識・経験を活かし、こうした相続にまつわる多様な問題に真摯に取り組んでおります。
遺言書の作成や遺産分割協議はもちろん、不動産の取り扱い、事業承継に関するご相談も承っております。
| 定休日 | 日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」より徒歩5分 都営地下鉄三田線「内幸町駅」より徒歩3分 JR「新橋駅」より徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」より徒歩7分 |
| 対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
| 電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 土曜 10:00~18:00 |
| 着手金 | |
| 報酬金 |
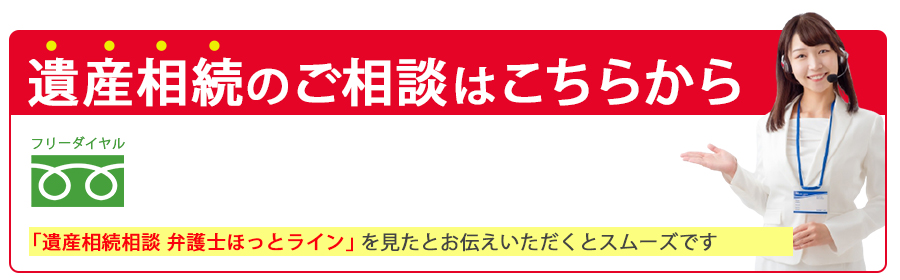
【対応分野】ときわパートナーズ法律事務所
相続・不動産・事業承継に強い弁護士が、実務経験を活かしてサポートします
長年の会社勤務で培った実務経験と交渉力、士業ネットワークを活かし、相続に関する複雑な課題に対応しています。
不動産や事業承継など、専門的な知識が求められる相続問題も、安心してご相談いただけます。
不動産・企業法務の実務経験を活かした相続サポート
会社員時代には、約15年間にわたり遊休地の開発など不動産関連業務に携わってきました。相続では不動産の取り扱いが重要なテーマとなることが多く、売却・管理・分割などについても、実務に基づいた具体的なアドバイスが可能です。
また、企業法務の経験も豊富で、事業承継や事業譲渡に関する知識を活かし、中小企業の相続対策にも対応しています。事業承継税制の活用や、財団・持株会社の設立など、経営者の方からのご相談も多数いただいております。
弁護士は代理人として交渉を行いますが、私は会社員時代に「当事者」として取引先と直接交渉してきた経験があります。そのため、弁護士としての視点に加え、実務者としての柔軟な交渉力も強みです。
専門家との連携で実現する、安心の相続支援
相続には、「不動産」「税務」「登記」など、幅広い専門知識が求められます。たとえば、賃貸物件を相続された場合には、その管理方法や運用方針についても慎重な検討が必要です。
しかし、不動産業者にもそれぞれ得意分野があり、大規模物件に強い方、小規模物件に精通している方、売買・仲介・賃貸それぞれに専門性があります。また、税理士や司法書士においても、相続に強い方と法人税務や商業登記に強い方では対応力が異なります。
こうした専門性の違いを踏まえ、相続に関するご相談では、適切な専門家と連携することが非常に重要です。当職は、これまでの実務経験を通じて築いてきた士業との信頼関係と連携体制を活かし、ご依頼者のニーズに最も適した専門家をご紹介・連携のうえ対応いたします。税理士・司法書士・不動産業者など、分野ごとのプロフェッショナルと協力しながら、ワンストップで安心できる相続支援を目指しています。
相続トラブルを防ぐために──家族ができる準備と心構え
相続は、家族の絆が試される場面でもあります。介護や不動産、遺言書の有無など、さまざまな要素が絡み合い、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
ここでは、よくある相続トラブルの事例と、それを未然に防ぐために家族ができることをご紹介します。
介護を担う家族とそうでない家族の間で起こる相続トラブル
兄弟姉妹のうち、誰かが親と同居し介護を担っている場合、相続時に不公平感が生じやすく、トラブルの火種になることがあります。
実際、「他の兄弟と揉めたくない」との理由で、介護をしている方から相続のご相談をいただくケースは少なくありません。「兄弟仲が良ければ大丈夫」と思われがちですが、相続には金銭が絡むため、感情的な対立が起こることもあります。兄弟間だけでなく、配偶者が関与することで話し合いが複雑化することもあります。
最近では、インターネットで相続情報を調べてから来所される方が増えていますが、「寄与分」「特別受益」「相続人の範囲」などについて誤解されているケースも多く見受けられます。たとえば、「親を介護したから多く遺産をもらえるはず」と考える方もいますが、家庭裁判所では寄与分として認められる金額はごくわずかです。
そのため、当職は介護を担った方に制度の限界を丁寧に説明し、他の相続人には介護の労苦に報いる形で公平な分配ができるよう、調整と交渉を進めています。
遺言書の作成が相続トラブルの予防につながる
親が一人暮らしをしていた家が空き家になった場合、売却して現金化するのが合理的な選択肢です。しかし、「思い出が詰まっているから売りたくない」「自分たちで持っていたい」といった感情が絡むと、話し合いが難航することがあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、親が元気なうちに遺言書を作成しておくことが有効です。とはいえ、「遺言書の話をすると、親に“自分の財産を当てにしているのか”と思われるのでは」と心配される方も多く、話題にすること自体が難しいのが現実です。
それでも、こうした心理的なハードルを乗り越えることが、将来の紛争を回避する第一歩になります。仮に最終的に遺言書を作成しないという結論になったとしても、親が生きているうちに家族で相続について話し合うことには大きな意味があります。相続は「いつか」ではなく、「今から」備えることで、家族の安心と信頼を守ることができます。
実際の相続事例から学ぶ──事業承継・特別受益・財団設立による相続対策
相続には、税務・不動産・家族関係など多くの要素が絡み合い、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
ここでは、当職が実際に対応した相続事例をご紹介し、具体的な解決策や交渉のポイントをお伝えします。
【事例1】事業承継税制と持株会社設立による相続税対策
ご依頼者は、父親から中小企業を承継し、全株式を単独で保有していた60代の男性でした。将来的に発生する相続税によって、子どもたちが会社の株式や不動産を手放さざるを得ない事態を強く懸念されていました。
そこで当職は、事業承継税制の活用と持株会社の設立をご提案。これにより、資産を売却することなく、親族による経営の継続を可能とする相続対策を実現しました。
結果として、ご依頼者の意向通り、会社の将来とご家族の生活を守る形での事業承継が整いました。
【事例2】家庭裁判所で特別受益を認定──不公平な財産使用への対応
ご依頼者は、父親を亡くされた50代の男性でした。遺言書には、ご依頼者と姉がそれぞれ遺産の半分を相続する旨が記されていました。しかし、父親と同居していた姉が父親の財産を自身のために使用し、都内の高級マンションを購入していたことが判明。
遺産分割協議は難航し、当職が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましたが、調停は不成立。最終的に遺産分割審判に移行し、裁判所は姉による特別受益を認定しました。ご依頼者は、本来受け取るべき相続分を取り戻すことができました。
この事例は、相続人間での不公平な財産使用が争点となった典型例であり、法的手続きを通じて適正な分配が実現されたケースです。
【事例3】財団法人設立による想いと不動産の継承
ご依頼者は、音楽活動を共にしていた夫を亡くされた50代の女性でした。夫には先祖代々受け継いできた広大な住宅と財産があり、夫妻はそこに暮らしていましたが、子どもはおらず、相続人も不在。
当初は、夫の親族に相続させる遺言書の作成を検討されていましたが、相続税の支払いによって不動産が売却され、マンション開発用地になる可能性が懸念されました。そこで当職は、若者の音楽活動を支援する財団法人の設立をご提案。財団に財産を承継させることで、亡き夫の音楽への想いと大切な不動産を守ることができました。
このように、相続の目的が「資産の継承」だけでなく「想いの継承」である場合、財団法人の活用は非常に有効な選択肢となります。
遺言書の悩みは一人で抱えず、相続の専門家にご相談を
「親に遺言書を書いてもらった方がいいのだろうか」
そんな悩みを、誰にも打ち明けられずに抱えている方も少なくありません。
まずは、家族で相続について話し合うことから始めてみませんか。遺言書があることで、親御様が亡くなられた後の相続トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
「遺言書は自分で自由に書ける」と思われている方もいらっしゃいますが、記載方法に不備があると無効になるリスクがあります。また、相続税の優遇制度などを知らずに作成してしまうと、結果的に損をしてしまう可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためにも、弁護士が遺言書の内容や形式を確認し、法的に有効かつご家族の意向に沿った形で整えるサポートを行うことが重要です。加えて、税理士などの専門家と連携しながら、税務面でも最適なアドバイスをご提供できます。
相続は、単なる財産の分配にとどまらず、家族の関係性や将来の安心にも深く関わる重要なテーマです。ご自身のことはもちろん、親御様の相続や事業の承継についても、悩みを一人で抱え込まず、相続に精通した弁護士に相談することが、安心への第一歩となります。
法律・税務・家族関係など、複雑に絡み合う相続の課題に対して、専門的な視点から、あなたとご家族にとって最も適した選択肢をご提案いたします。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。