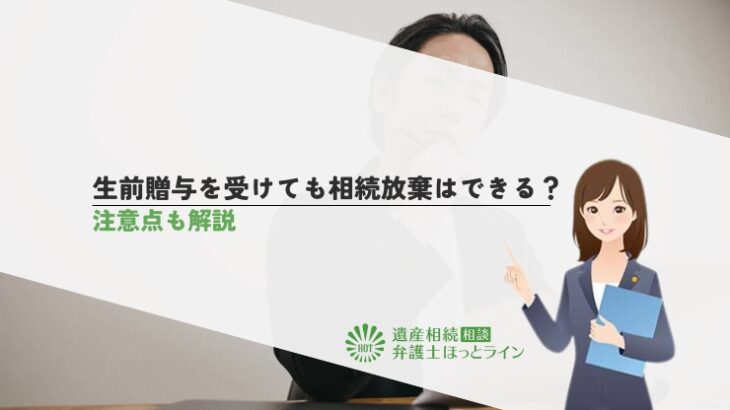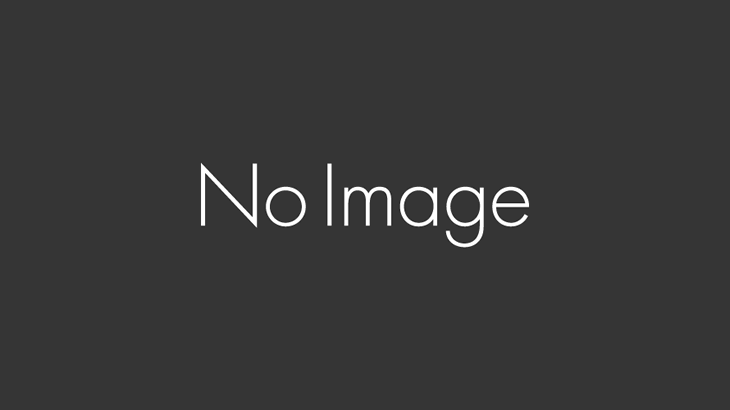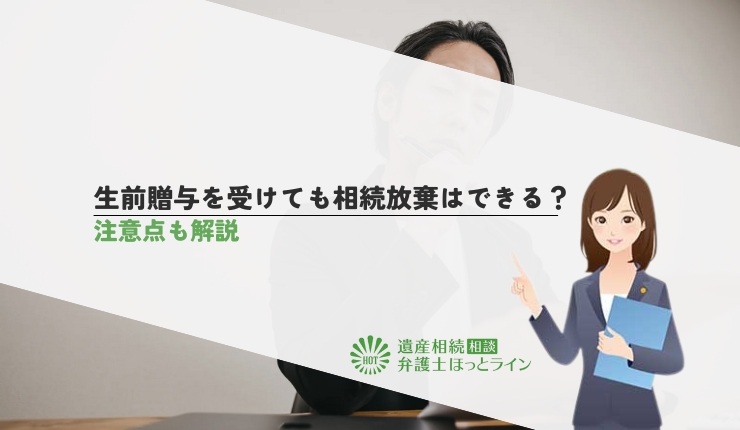
「生前贈与を受けているけれど、相続放棄はできるの?」
生前贈与を受けた人が相続放棄できるのかと疑問に思うことがあるかもしれません。
もっとも、注意しておくべき点もいくつかあります。
この記事では、生前贈与を受けた人が相続放棄をできるのか、その際の注意点などについて解説しています。
目次
生前贈与を受けた場合でも相続放棄はできる?
生前贈与を受けているから相続放棄ができないということはありません。
まずは、生前贈与と相続放棄の意味について、正確に把握しましょう。
生前贈与とは
例えば、生前贈与には、親が子どもに対して財産を贈与するケースや、夫が妻に対して財産を贈与するケースなどがあります。
生前贈与は特別な法的手続きではなく、あくまでも生前に財産を贈与することを指す言葉に過ぎないので、裁判所などでの特別な手続きは不要です。贈与のための契約書等の書類が必要ということもありません。
暦年課税という原則的な贈与税の課税方法を選択している場合には、年間110万円以内の贈与に限り非課税とされます。逆にいえば、年間110万円を超える部分の贈与に対しては贈与税がかかります。
なお、年間110万円以内の贈与しかなされていない場合には、贈与税の申告は不要です。
相続放棄とは
相続放棄をすれば、借金や債務などのマイナスの財産はもちろん、預貯金や不動産などのプラスの財産についても全て受け継がないこととなります。
また、相続放棄をすれば、相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続手続から外れることが可能となります。
相続放棄は、特別な法的行為であるため、家庭裁判所において所定の手続きをしなければなりません。単に裁判所外で相続放棄をしたい旨の意思表示をするだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
生前贈与を受けたうえで相続放棄をすることは可能
生前贈与を受けている以上、被相続人から財産を受け継ぐべきであって、相続放棄は許されないと考える人もいるかもしれません。
しかし、法律上は、生前贈与と相続放棄は全く別の手続きです。それぞれ独立した手続きであることから、生前贈与を受けたうえで相続放棄をすることは可能です。
生前贈与を受けたのに相続放棄をするケースとは
生前贈与を受けていたのに相続放棄をするケースには、例えば、次のようなものが考えられます。
- 被相続人の生前には財産に余裕があったため生前贈与を受けていたものの、亡くなる直前に大幅に財産状況が悪化して、多額の借金を背負うようになってしまった
- 被相続人は生前贈与をしてくれていたため、財産状況に余裕があるものと思われていたが、死後に遺産調査をしたところ予期せぬ借金が発見された
- 被相続人は経済的に余裕があり、生前贈与をしてくれていたが、相続が発生してから相続人間で相続争いが発生し、自分は相続争いに巻き込まれたくない
これらのほかにも、相続放棄をしたい理由にはさまざまなものがあり、生前贈与を受けていたが相続放棄をしたいということはあり得るでしょう。
相続放棄には期限もあることから、相続放棄をしたいと思ったら、生前贈与を受けていたとしてもためらうことなく手続きを進めることが大切です。
生前贈与を受けた後に相続放棄を行う際の注意点
生前贈与を受けた後に相続放棄を行う際にはいくつか注意しておきたい点があります。
生前贈与を受けた後に相続放棄を行う際の注意点についてご説明します。
相続放棄は3か月の熟慮期間内に手続きを行う必要がある
相続放棄は、原則として、相続が開始したことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。この3か月という相続放棄の期限を熟慮期間といいます。
相続放棄の手続きを完了させないまま3か月の熟慮期間が経過してしまうと、原則として相続放棄が認められなくなってしまいます。
また、相続放棄は管轄の家庭裁判所で所定の書類を提出するなどして手続きをしなければならないため、ある程度準備に時間がかかってしまいます。
なお、遺産が膨大であるなどして3か月の熟慮期間が経過してからようやく借金の存在を把握できた場合などには、3か月の熟慮期間を過ぎてからでも相続放棄が認められることがあります。
このようなケースで相続放棄を認めてもらうためには裁判所に事情を詳しく正確に伝えて納得してもらう必要があります。ご自身だけでは難しいことも多いため、弁護士に相談・依頼して相続放棄の手続きを代行してもらうのがおすすめです。
いったん相続放棄をしてしまうと取り消すことができない
相続放棄は、いったん行ってしまうとあとから取り消してやっぱりなかったことにするということはできません。
生前贈与後に相続放棄をすることについては、「生前贈与を受けていたのに相続放棄をするのはおかしい」などと他の相続人に言われてしまうことが考えられます。
そのような言葉に納得したとしても、後から相続放棄をなかったことにするということはできません。
相続放棄をするかどうかを決めるにあたっては、後から取り消せないということに十分留意したうえで、慎重に判断することが必要です。
遺産を処分等すると相続放棄が認められないことがある
相続放棄を予定していた相続人が被相続人の遺産の一部である預貯金を使い込んでしまうなど、遺産の処分行為を行ってしまうと、遺産を無条件に受け継ぐことにしたものとみなされて(このことを「法定単純承認」といいます)、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。
法定単純承認が認められる事由には、次のようなものなどがあります。
- 被相続人の預貯金など遺産の一部を使い込んでしまう行為
- 被相続人の借金を遺産の一部を使って返済する行為
- 名目は形見分けとしてであっても、遺産のうち形見分けの範囲を超える高価な財産的価値を有するものを受け取る行為
基本的には、遺産を処分する行為が法定単純承認事由に該当します。相続放棄を考えているのであれば、法定単純承認事由に該当する行為をしてしまわないように、十分に注意しましょう。
なお、ある行為が法定単純承認事由に該当する遺産の処分であるかの判断は微妙なところが多いものです。相続放棄を予定しているものの、遺産の一部を使う必要が生じた場合などには、どこまでの行為なら差し支えないのか弁護士に相談してみるようにしましょう。
生前贈与に関して詐害行為取消権の行使を受ける可能性がある
例えば、親から子どもが生前贈与を受ける場合において、生前贈与時に親に多額の借金があって財産状況がマイナスであるということを子どもが知っているということがあります。
このような場合で親が亡くなってから相続放棄をすると、借金の債権者による「詐害行為取消権」の行使を受ける可能性があります。
債務者がわざと財産を減少させる行為をしたり、一部の債権者にのみ過度に偏った弁済行為をしたりした場合には、債権者が債権を行使して全て回収できなくなってしまうおそれがあります。このようなことから、詐害行為を取り消す権利が債権者に認められているのです。
例えば、親がプラスの財産として500万円の預貯金を有している一方、同時に1,000万円の借金を有していたとします。また、親子ともにこのような財産状況を知っていたとします。
この場合に、500万円の預貯金を全て子どもに贈与してしまうと、親が借金を返すためのお金がなくなってしまい、債権者が借金を返してもらうことが困難になってしまいます。
このケースで債権者が詐害行為取消権を行使すれば、相続放棄をしたかどうかに関わりなく、生前に行われた贈与行為を取り消されてしまう可能性があります。
詐害行為取消権の行使によって生前贈与が取り消された場合には、生前贈与を受けた側は受けた贈与に相当する額を返還しなければならないなどの影響があります。
生前贈与を受けた財産に関して相続税がかかることがある
相続税の負担は、相続放棄をしたから逃れられるというものではありません。このため、生前贈与の時期に着目して相続税の負担があるかどうかを判断し、必要に応じて相続税を納めなければなりません。
暦年課税の元では、相続税が発生する生前贈与とは、相続が開始する前より7年以内の生前贈与です(2024年1月1日以降の制度)。
相続が開始する前7年以内になされた生前贈与の贈与財産は、相続税の課税対象となる財産に含めなければならず、この期間内に多額の生前贈与がなされていれば、相続税を納めなければならない可能性があります。
また、暦年課税ではなく「相続時精算課税制度」の適用を受けていた場合には、これとは異なる処理がなされることとなります。
相続時精算課税制度の適用を受けていた場合には、2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税となりますが、その後の相続開始時に贈与を受けた分を全て相続税の課税対象として計算しなければなりません(ただし、2024年1月以降、年間110万円の基礎控除があります)。
相続時精算課税制度は、あらかじめ税務署にその制度の適用を受けるため旨の申請をしておく必要があります。このため、税務署としても、相続税の申告と納税を行わなければならないことを把握しています。
相続税の申告と納税は、ご自身だけでは正確に判断することが難しいものであるため、少しでも不安があれば、税理士や相続に詳しい弁護士に相談するようにするとよいでしょう。
「生前贈与後の相続放棄」以外に負債を受け継がせない方法
被相続人の借金を受け継がないようにする方法は、「生前贈与後の相続放棄」だけではありません。
ほかにも方法があります。このことについてご説明します。
財産を遺す側が生きている間に「債務整理」で借金を整理する
財産を遺す側が借金を抱えている場合には、生きている間に「債務整理」を行うのがおすすめです。
債務整理には、大きく分けて、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があり、借金の状況に応じて適切な方法が異なります。
これは裁判所を通さないで任意に債権者と交渉して借金を減額してもらうものです。裁判所を通さなくて済む分柔軟に条件を交渉できますが、借金の減額幅は限定的なものになりがちであるという特徴があります。
免責許可決定さえ出れば、基本的に負っていた債務の全てが免除されるため、その後の経済的な立ち直りに向けて大きな効果が期待できるという特徴があります。
一般的には、借金の額が預金などのプラスの財産の額を大きく超えており、借金を返していける見込みが立たないような場合には、積極的に自己破産を選択することが望ましいといえます。
もっとも、どのケースでどの手続きを取るのがよいのかは人それぞれ異なります。具体的にどうするべきかについては、弁護士に相談するのがよいでしょう。
いったん自己破産をして借金を免除してもらえば、その後に得た収入であらためて貯金をしていくことができます。貯金ができれば生前贈与の原資にもなるので、返し終えられる見込みの少ない借金を返し続けるよりは良いと考えることもできます。
また、自己破産をして借金を帳消しにしておけば、その後の相続開始時には、相続人が相続放棄を選択しなくても済むことにもなり、遺産を受け継げることにもつながります。
債務整理は、早ければ早いほど良いです。債務整理が必要かもと思ったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
相続時に「限定承認」を行う
相続開始時にはプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしていないことは多くあります。そのような場合に、限定承認をしておけば、仮にマイナスの財産が非常に多かったとしてもマイナスの財産を受け継ぐことにはなりません。
また、仮にプラスの財産のほうが多かった場合には、マイナスの財産を返済した残りのプラスの財産は受け継ぐことができます。
このように、限定承認はなかなか良い方法のようにも思えますが、一方で定められた手続きが非常に手間で複雑であり簡単に行うことができないという大きなデメリットがあります。
限定承認をしたいと考えたとしても、安易に行うのではなく、まずは弁護士に限定承認をするのが適切かどうかを相談してみるようにしましょう。
まとめ:生前贈与を受けていても相続放棄はできる
「生前贈与を受けていると相続放棄ができないのでは?」と思ってしまうかもしれませんが、そのようなことはありません。
生前贈与を受けていても相続放棄はできるので、相続放棄が必要だと思ったらためらうことなく手続きに踏み切ることが大切です。
どのようにするのがよいのかアドバイスをくれるだけでなく、依頼すれば手続きを代理して行ってくれます。
弁護士に依頼して、スムーズに生前贈与後の相続放棄を成功させましょう。