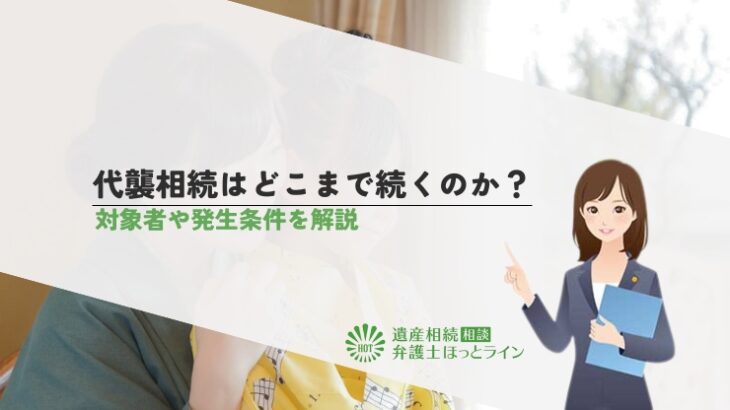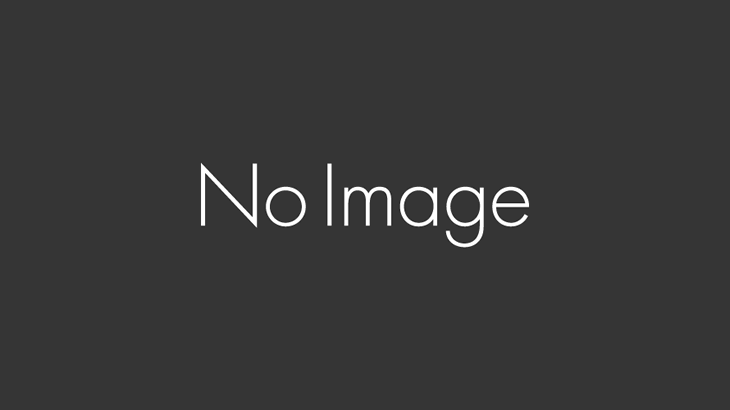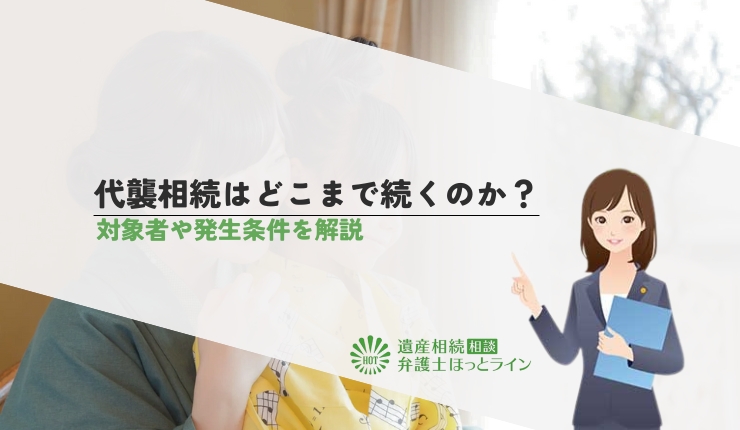

三上 貴規
代襲相続とは
代襲相続制度の概要
たとえば、親A、子B、孫Cがいるとします。
Aが死亡し相続が開始した時点で、本来の相続人であるBが既に死亡していた場合、CがBの代わりに相続人となります。
代襲相続するCを「代襲相続人(代襲者)」、代襲相続されるBを「被代襲者」と呼びます。
代襲相続制度が存在する理由
代襲相続制度が存在する理由は、公平のためであるとされています。
親A→子B→孫Cの順序で相続が発生した場合、原則としてCはAの財産を引き継ぐことができますし、Cもそれを期待していると考えられます。
たまたまAが亡くなる以前にBが亡くなっていた場合に、CがAの財産を引き継ぐことができないとすると、それは不公平といえます。
そこで、代襲相続制度を設けることにより、CがAの財産を引き継ぐことができることとしたのです。
代襲相続人になれる人
代襲相続人になれるのは、①被相続人(亡くなった人)の孫、②被相続人の甥・姪などです。
後述するように、①の場合は再代襲も可能です。
被相続人の孫(再代襲あり)
前述の親A、子B、孫Cの事例でCが代襲相続人となったように、被相続人の孫は代襲相続人となることが可能です。
この場合、Cの子(Aからみたひ孫)Dがいれば、Dが代襲相続人となることが可能です。
このように、代襲相続人の子がさらに代襲相続することを「再代襲」といいます。
なお、ひ孫Dも既に死亡していた場合、Dの子(Aからみた玄孫)Eが代襲相続人となること(再々代襲)も可能です(民法第887条第3項)。
被相続人の甥・姪(再代襲なし)
被相続人に子や両親がいない場合などには、兄弟姉妹が相続人となります。
本来であれば兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が死亡していたときには、その子(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続人となります。
たとえば、X、Xの弟Y、Yの子(Xからみた甥・姪)Zがいるとします。
Xが死亡し相続が開始した時点で、本来の相続人であるYが既に死亡していた場合、ZがYの代わりに相続人となります。
このように、被相続人の甥・姪も代襲相続人となり得ますが、甥・姪が死亡していたとしても再代襲は発生しません。
先ほどの事例で、Zが既に死亡していたとしても、Zの子が再代襲することはありません。
姪・甥の子に再代襲が認められていないのは、生活関係が希薄な人にまで相続人の範囲を拡大するのは妥当ではないからと説明されています。
代襲相続人が養子の子である場合
養親A、養子B、Bの子Cがいるとします。
民法第887条第2項ただし書は、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないと定めています。
CがAB間の養子縁組「前」に生まれた場合には、CはAの直系卑属には該当しません。この場合、Cは代襲相続人となることはできません。
一方、CがAB間の養子縁組「後」に生まれた場合には、CはAの直系卑属に該当します。この場合、Cは代襲相続人となることができます。
なお、このことは、甥・姪が代襲相続人となるケースでも同様です。
代襲相続が発生する条件
代襲相続が発生するためには、代襲原因と呼ばれる条件が必要です。
代襲原因は、
- 1.被代襲者が相続開始以前に死亡したこと
- 2.被代襲者が相続欠格に該当すること
- 3.被代襲者が相続廃除されたこと
のいずれかです(民法第887条第2項)。
ここまでは、被代襲者(本来の相続人)が相続開始以前に死亡した事例を用いて説明してきましたが、死亡以外にも相続欠格に該当する場合や相続廃除された場合にも代襲相続が発生するのです。
被代襲者が相続の開始以前に死亡したこと
被相続人の死亡以前に、本来の相続人である子や兄弟姉妹が死亡していると代襲相続が発生します。
親A、子B、孫Cの事例でいえば、被相続人Aの死亡以前に、本来の相続人であるBが死亡していると代襲原因が存在することになります。
なお、被相続人の死亡「以前」ですので、AとBが同時に死亡した場合にも代襲原因が存在することになります。
被代襲者が相続欠格に該当すること
相続に関して一定の不正行為を行うと、相続人となる資格を剥奪されます。
これを「相続欠格」といいます。
民法は相続欠格に該当する人を次のように定めています(民法第891条)。
- 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く)
- 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
親A、子B、孫Cの事例でいえば、BがAを故意に殺害した場合、Bは相続欠格に該当し、相続人となる資格を剥奪されます。
Bが相続欠格に該当することで代襲相続が発生し、CがBに代わって相続人となります。
被代襲者が相続廃除されたこと
相続欠格と異なり、被相続人が請求しなければ相続人となる資格が剥奪されることはありません。
被相続人が相続廃除の請求をできるのは次のいずれかの場合です(民法第892条)。
- 1.被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
- 2.その他の著しい非行があったとき
親A、子B、孫Cの事例でいえば、BがAを虐待したり、重大な侮辱を加えたりした場合、AはBの相続廃除を請求することができます。
Aの請求が認められると、Bの相続人となる資格は剥奪されます。
Bが相続廃除されたことで代襲相続が発生し、CがBに代わって相続人となります。
代襲相続に関するQ&A
被相続人の配偶者の連れ子は代襲相続人になることができますか?
たとえば、被相続人E、その妻F、Fの連れ子Gがいるとします。
Eが死亡した際に、Fが生存していれば、FはEの相続人となります。
一方で、Fが既に死亡していたとすれば、Fが相続人となることはありませんし、Gが代襲相続人となることもありません。
なお、EとGが養子縁組をしていた場合には、GはEの相続人となることができます。
ただし、これは代襲相続が発生するからではありません。
養子縁組によって、Gが法律上Eの子として扱われるためです(民法第727条)。
配偶者は義理の両親の相続の際に代襲相続人となることができますか?
たとえば、親H、子Iがおり、Iに妻Jがいるとします。
この状況で、Iが死亡し、その後Hが死亡したとしても、JがHの相続について代襲相続人となることはありません。
祖父母は孫の相続の際に代襲相続人となることができますか?
この場合に、BがAよりも先に死亡していたときには、CはAの相続人となります。
これは、Cが代襲相続人となるからではなく、Aの直系尊属として相続権を有するからです(民法第889条第1項第1号)。
代襲相続人が複数いる場合の相続分はどうなりますか?
Xに子Y1、Y2がおり、本来であればXの相続の際にY1、Y2が2分の1ずつの相続分で相続するものとします。
まず、Z1、Z2はY1を代襲して代襲相続人となります。
この場合のZ1、Z2の相続分は、被代襲者であるY1の本来の相続分を法定相続分で分けた割合となります(民法第901条)。これを「株分け」と言います。
したがって、Z1、Z2の相続分はそれぞれ4分の1となります。
なお、Y2の相続分は変わらず2分の1となります。
胎児も代襲相続人となりますか?
たとえば、親A、子Bがおり、Bの妻が胎児Cを身ごもっていたとします。
Aが死亡した時点でCはまだ生まれていません。
前述のルールからすると、Aの相続が開始した時点でCは「存在している」とはいえず、代襲相続人となることはできないようにも思えます。
しかし、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます(民法第886条第1項)。
したがって、胎児CもAの相続については既に生まれたものとみなされ、代襲相続人となることができます。
ただし、胎児が死体で生まれたときは代襲相続人となることができません(民法第886条第2項)。
被相続人の子と孫のどちらが先に死亡したのか不明である場合に代襲相続は発生しますか?
しかし、被相続人と被代襲者の死亡の先後が不明な場合もあり得ます。
親A、子B、孫Cの事例でいえば、AとBが同じ飛行機事故で死亡して、どちらが先に死亡したのか(あるいは同時に死亡したのか)が不明といった場合です。
このような場合について、民法には「同時死亡の推定」という規定があります(民法第32条の2)。
この規定では、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」とされています。
つまり、AとBの死亡の先後が不明な場合には、AとBは同時に死亡したものと推定されます。
代襲相続は被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合にも発生するため、前述の事例においてCは代襲相続人となります。
被相続人の子が相続放棄した場合、孫は代襲相続人となることができますか?
したがって、被相続人の子が相続放棄したとしても、孫が代襲相続人となることはありません。
親A、子B、孫Cの事例でいえば、Bが相続放棄したとしても、Cが代襲相続人となることはありません。
代襲相続人に遺留分は認められますか?
被相続人の子を代襲した代襲相続人には遺留分が認められています。
たとえば、親A、子B、孫Cの事例で、Cが代襲相続人となる場合には、Cには遺留分が認められます。
一方、被相続人の兄弟姉妹を代襲した代襲相続人には遺留分は認められていません。
たとえば、X、Xの弟Y、Yの子(Xからみた甥・姪)Zの事例で、Zが代襲相続人となる場合には、Zには遺留分は認められません。
まとめ
以上のように、代襲相続に関するルールは複雑であるため、代襲相続が発生するのかや相続分がどうなるのかなどを正確に判断するためには専門的な知識が必要です。
代襲相続に関してお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。