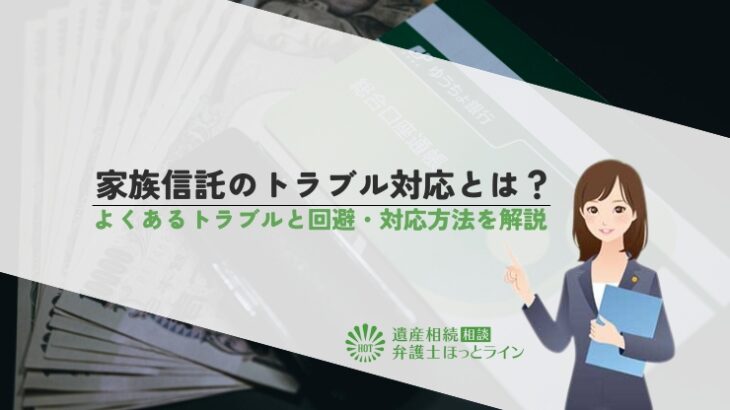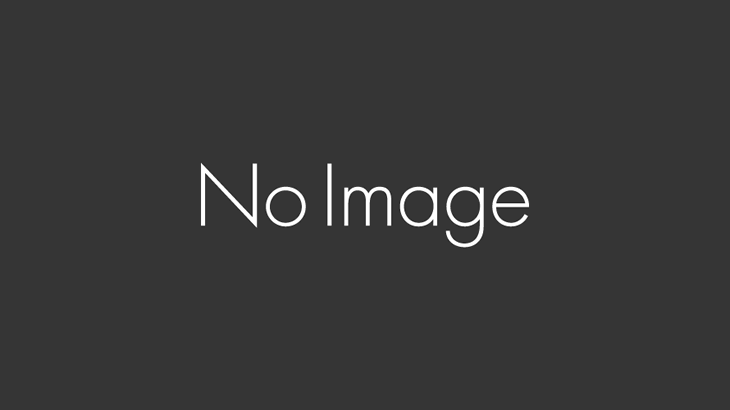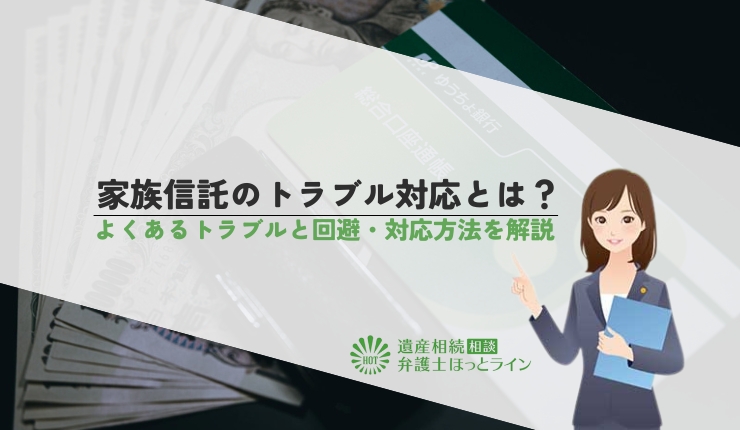
老後に備えて家族信託を活用する事例が増えています。
家族信託は、一見有用な仕組みに見えるかもしれませんが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルを引き起こす可能性があり、トラブルに対して適切に回避・対応することが重要です。
この記事では、家族信託のよくあるトラブルと回避・対応方法について解説しています。
目次
- 1 家族信託とは何か
- 2 家族信託のメリット
- 3 家族信託のデメリット
- 4 家族信託でよくあるトラブル
- 4.1 専門家に任せず自分だけで信託契約書を作成してトラブルになる
- 4.2 知識・経験が十分でない専門家に家族信託を任せてしまう
- 4.3 必要がないのに家族信託を利用してしまう
- 4.4 家族間で十分な話し合いをしないまま家族信託を進めてトラブルになる
- 4.5 想定外に高額な税金を納めることになる
- 4.6 信託できない財産を家族信託の対象としてしまう
- 4.7 「1年ルール」で想定外に早く家族信託が終了してしまう
- 4.8 「30年ルール」で意図せず家族信託が終了してしまう
- 4.9 親の認知症などが進んで家族信託の契約を締結できなくなる
- 4.10 遺留分侵害を考慮せず家族信託を組んでしまう
- 4.11 信託財産以外との損益通算ができず納める税金が増える
- 4.12 抵当権が設定された不動産を無断で信託してローンの一括返済を求められる
- 4.13 家族信託以外の認知症・相続対策ができていない
- 5 家族信託のトラブルを回避・対応する方法
- 6 家族信託の組成やトラブル対応を依頼できる専門家
- 7 まとめ:家族信託のトラブル対応は弁護士に相談・依頼しよう
家族信託とは何か
「家族信託」とは、例えば親が認知症になるなどして自分で財産を管理・処分ができなくなった時などに備えて組まれる信託であり、元々財産を有していた人の所有権のうち「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・処分する権利」を分離して目的に応じて家族間で割り振り、財産を管理等する信託契約のことです。
家族信託は、認知症対策などの目的で最近活用されることが増えている信託契約の一種です。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託は、その名のとおり「家族の間で財産を信じて託す」契約です。
家族信託では、次の3つの役割の人が登場します。
- 委託者:財産を元々所有しており、その財産の管理・処分を家族の誰かに任せる人
- 受託者:財産の管理・処分等の権限を委託者から任された人
- 受益者:信託によって管理・処分を任された財産から利益を受ける権利を有する人
例えば、家族信託では、親が委託者かつ受益者となり、子どもが受託者となることがあります。この場合には、親が元々有していた預貯金や不動産などの財産の管理・処分等を子どもに任せ、子どもがその財産を管理・運用するなどし、得られた利益を受益者である親が受け取ることとなります。
家族信託が活用されるケース
家族信託は、次のようなケースなどで活用されることがあります。
- 親が認知症になってしまった際に親の資産が動かせなくなることを避けたいケース
- 子どもや孫の世代まで誰に親の財産を受け継がせるかを指定したいケース
- 重い病気や障害を有する子どもの生活を経済的に保障したいケース
このように、家族信託が活用されるケースにはさまざまなものがあります。
多いのは親の認知症に備えるケースですが、それ以外にも家族信託を活用できるケースはいくつもあるため、必要に応じて家族信託の活用を検討することで適切に目的を達成できます。
家族信託のメリット
家族信託には、「家族信託ならでは」のメリットがあります。このメリットを活かすことで、家族信託を有効に活用して目的を達成できます。
親が認知症になってもその影響を受けずに財産を管理できる
親が認知症になると、適切に自分の財産を管理できなくなることがあります。また、症状の程度によっては、不動産を売却するための契約を単独で締結できなくなることもあるでしょう。
こうなると、親が生きているのにその預貯金を使えなくなったり不動産を処分できなくなったりしてしまい、親の財産を動かせなくなってしまいます。
家族信託を活用すれば、親の認知症の程度に関わらず受託者が委託者である親の財産を管理・処分することが可能となるため、親の認知症に備えて柔軟に財産を動かせる状態を維持できるようになります。
成年後見制度を利用するより柔軟に財産管理等を行うことができる
親が認知症になった場合に取ることのできる手段として、成年後見制度もあります。成年後見制度を利用すれば、親は成年被後見人となって成年後見人がつき、成年後見人が親の代わりに財産の管理などを行います。
家族信託であれば、委託者(親)の基本的な方針に従うものの、受託者(子どもなどの家族)が大きな裁量を持って財産の管理・処分等を行うので、成年後見制度を利用する場合よりも柔軟に財産管理を行うことができるという特徴があります
委託者の意向に従って財産を受け継がせることができる
家族信託は、遺言に似た効果を持たせることもできます。
あらかじめ信託契約において財産から利益を受ける権利を受け継がせる人を定めておけば、遺言を残した場合と同様にその権利を受け継がせることができます。
特に、遺言では、次に受け継ぐ者を指定できるにとどまるのに対し、家族信託では遺言と異なり、次に受け継ぐ者だけでなく、さらにその次に受け継ぐ者についても定めることができます。
これにより、遺言の場合と比べてより委託者の意向に従った財産の承継を実現することが可能となります。
共有財産である収益不動産の経営権限を一人に集中させることができる
昔に親から受け継ぐなどして収益不動産(投資用マンションなど)が高齢の兄弟姉妹間で共有状態になっている場合、共有不動産の賃貸契約等は共有者全員で行わなければならないことから、共有者のうち一人でも認知症等により十分な意思表示ができなくなったときには共有不動産の管理処分が難しくなってしまいます。このことは、投資上、大きなリスクです。
このため、家族信託を活用して収益不動産の受託者を最も信頼できる一人に集中させることで、その一人に収益不動産の経営権限を集中させ、他の共有者の認知症等の影響を受けないようにすることが可能となります。
信託契約の倒産隔離機能を活用できる
信託契約により受託者が委託を受けた財産(信託財産)は、受託者の固有の財産とは分けて取り扱われます。このため、万が一受託者が差押えを受けたり倒産したりする事態になっても、信託財産はその対象となりません。このように、信託契約には、委託者の財産を倒産などから隔離する機能があります。
家族信託のデメリット
家族信託に馴染みがなく親の理解が得られないことがある
そもそも、「家族信託」という制度は、遺言や成年後見制度などと比べてもまだ一般社会にあまり馴染みがないものです。
このため、子どもが家族信託の活用を提案しても、親が十分に理解してくれず、家族信託を組むことに反対するなどして家族信託の活用そのものができないことも多くあります。
家族信託では身上監護ができず成年後見制度を利用する必要がある
家族信託では、受託者が委託者の身上監護をする権限がありません。身上監護とは身の回りの世話に関する契約をする権限です。このため、例えば、認知症になった親が入院したり施設に入居したりする場合のその契約については、子どもが受託者になっていたからといって親の代わりに行えるわけではありません。
成年後見制度は、親が認知症などになった後に利用を開始するものですが、認知症などになる前であれば、任意後見契約を締結してあらかじめ信頼できる子どもなどを将来の後見人として定めておくこともできます。
受託者の責任が重く引き受ける家族がいないことがある
家族信託の受託者は、委託者の財産を適切に管理・処分等しなければならないため、責任が重いです。
このため、家族信託を組もうと思っても子どもが誰も受託者を引き受けてくれないということもあります。受託者が見つからなければ家族信託を組むことはできません。
家族間で家族信託をめぐる争いに発展するリスクがある
家族信託は、親の財産を子どものうちの一人が受託者として管理するものであるため、他の子どもが「適切に財産を管理されていないのではないか」「財産を使い込んでいるのではないか」などと不安になってしまうことがあります。
これにより、家族信託をめぐる争いに発展するリスクがあります。
家族信託でよくあるトラブル
家族信託でよくあるトラブルについてご説明します。まずはよくあるトラブルを押さえて、トラブルに陥らないように十分に注意しましょう。
専門家に任せず自分だけで信託契約書を作成してトラブルになる
家族信託は、信託契約というあまり一般に馴染みのない契約を締結した上で組まなければならないものです。特に法律の専門家以外で信託契約について十分な知識を有している人はかなり少ないでしょう。
インターネット上を検索すれば、信託契約書の書式やひな形を見つけることができるかもしれません。また、インターネット上の情報をもとに自分で信託契約書を作ってみようとする人もいるでしょう。
しかし、インターネット上のひな形や情報には不十分なものも多くあり、それらを参考にするだけでは問題のない家族信託契約書を作成することは難しいのが実情です。
自分で信託契約書を作ると、有効な信託契約の要件を満たさない契約書を作ってしまうこともありますし、契約条項の中に矛盾が生じてしまっていることも多くあります。
こうなると、将来的に家族信託をめぐるトラブルが発生するリスクを増やしてしまうことになりかねません。
知識・経験が十分でない専門家に家族信託を任せてしまう
家族信託は、普及してからまだ歴史の浅い制度であり、たとえ弁護士や司法書士などであっても十分な知識・経験を有していないことはよくあります。
このような知識が十分でない専門家に信託契約書の作成を任せてしまうと、有効な信託契約書を作成してもらえたものの将来のトラブル発生への対策が不十分だったり家族信託を組む際の他の家族への説明や協議が不十分だったりして、結果的にあまり上手に家族信託を組むことができないということにもなってしまいます。
必要がないのに家族信託を利用してしまう
メリットが少なかったり利用の必要がなかったりするのにわざわざ家族信託を利用してしまうと、家族信託を利用するための負担ばかりが大きくなってしまったり家族信託を利用するために必要な金銭的な支出のほうが大きくなってしまったりすることもあります。
こうなると、結果的に家族信託を利用しないほうがよかったということにもなりかねません。
家族間で十分な話し合いをしないまま家族信託を進めてトラブルになる
特に、家族信託は決して分かりやすい制度ではないため、家族間で十分な話し合いをしないまま家族信託を進めることは、後々大きな争いを生む原因となってしまう可能性が高いです。
想定外に高額な税金を納めることになる
家族信託では、信託スキームの設計内容や信託契約書の記載内容によっては、贈与税や所得税などの予想外の税金が発生してしまうことがあります。
これらの税金が発生しているのにそのことに気づかないままでいると、納税義務者が無申告に伴う加算税などのペナルティを課せられたり納税のためのお金が足りなくなったりするなど、大きな税務上のリスクが生じてしまうこともあります。
信託できない財産を家族信託の対象としてしまう
家族信託は、信託法という法律に基づいて設計・組成される信託であり、信託法をはじめとするさまざまな法律の規制を受けます。
家族信託を組む上では、法律上信託できない財産が信託の対象に定められていることがあり、結果的に家族信託が無効となることがあります。
信託できない財産を家族信託の対象としてしまうと、家族信託が無効となってあらためて家族信託をやり直さなければならなくなり、大きな手間がかかってしまいます。
「1年ルール」で想定外に早く家族信託が終了してしまう
「1年ルール」とは、受託者が唯一の受益者を兼ね、その状態が1年続くと信託契約が終了するというルールです。
1年ルールを認識していなければ、適切な家族信託の組成ができず、想定外に早く終了させてしまうことにもなりかねません。
「30年ルール」で意図せず家族信託が終了してしまう
家族信託の設計・組成によっては、信託契約を締結した当時の受益者(親など)が亡くなっても、その後に子や孫が受益者となって信託を引き継いでいくことができます。
第二、第三の受益者を定めておいたとしても、30年ルールの適用により最後の受益者まで信託が受け継がれることなく意図せず家族信託が終了してしまうことがあります。このことを正確に認識していなければ、当初思っていたとおりに信託を受け継がせていけないこともあります。
親の認知症などが進んで家族信託の契約を締結できなくなる
家族信託は契約の一種なので、親の認知症が進んで契約の締結ができない状態になっていると、もはや家族信託のための信託契約を締結することができません。
親の認知症をきっかけに家族信託の利用を考えた場合には、親の認知症が進んで契約を締結する能力がなくなる前に信託契約を締結しなければなりません。
家族信託の準備に手間取って時間がかかってしまうと、その間に親の認知症が悪化して契約を締結する能力を失ってしまい、結局家族信託に必要な信託契約を締結できずに終わってしまうことがあります。
遺留分侵害を考慮せず家族信託を組んでしまう
「遺留分」とは、一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことで、遺留分を侵害するような遺産分割・遺言がなされた場合には、遺留分権利者は遺留分侵害額を侵害者に対して請求できます。
遺留分侵害のことを考慮しない内容で家族信託を組んでしまうと、将来相続が発生した際に遺留分をめぐる相続争いの火種にしてしまうリスクがあります。
信託財産以外との損益通算ができず納める税金が増える
投資用アパートなどの収益不動産を信託財産とした場合には、その信託された収益不動産の収支が赤字だったとしても、信託していない黒字の不動産との間で損益通算をすることができません。
抵当権が設定された不動産を無断で信託してローンの一括返済を求められる
抵当権が設定された不動産を銀行などに無断で信託すると、ローンの一括返済を求められる可能性があります。
これは、信託契約により不動産の所有権が委託者から受託者に移転するためであり、ローン契約で所有者の変更が許されていなければ銀行などはローンの一括返済を請求できるようになるからです。
抵当権が設定された不動産について家族信託を組もうとする場合には、必ず融資を受けている銀行などに事前に相談することが必要です。
家族信託以外の認知症・相続対策ができていない
家族信託は魅力的な側面を有する仕組みである一方、家族信託の利用にばかり気を取られてしまい、家族信託以外の認知症・相続対策ができていないことがあります。
家族信託は万能な制度ではありません。場合によっては家族信託以外の生前対策を行っておくほうが有利になることもあります。
他の対策で十分なのに家族信託にこだわってしまうと、結果的により良い対策にならなかったということにもなりかねません。
家族信託のトラブルを回避・対応する方法
家族信託のトラブルを回避・対応する方法についてご説明します。
家族信託以外の認知症・相続対策も視野に入れる
家族信託以外にも、目的に合わせてさまざまな相続対策が存在します。
他の対策として、遺言や生前贈与、任意後見契約など、さまざまな方法を組み合わせることで意図している目的を達成できることもあります。
家族信託の知識や経験を十分に有している専門家に相談・依頼する
家族信託の知識や経験を十分に有しているかどうかは、専門家がどれだけ家族信託に関する情報を発信しているか、相談の際にどれだけ詳しく分かりやすく説明してくれるかなどから判断することができます。
「これまで家業の顧問を依頼してきたからその弁護士・司法書士に家族信託のこともお願いしよう」などの理由で安易に専門家を選んでしまいたくなるかもしれません。しかし、弁護士や司法書士であれば誰でもいいわけではないということは意識しておきましょう。
十分に家族信託の仕組みを理解した上で活用する
家族信託を組んだ結果として権利関係などがどのようになるのか、仕組みをしっかりと理解した上で活用することが大切です。しかし、家族信託はまだ十分に広く普及していない上に、信託という仕組み自体が理解することの難しい制度です。
家族の間で十分に家族信託について話し合って情報を共有する
親と一部の子どもだけの話し合いで家族信託を組んでしまうと、他の子どもや親族が「家族信託の話は聞いていない」などと主張してトラブルになりかねません。
関係する家族には幅広く家族信託について話し合い、情報を共有しておくことで、家族間のトラブルを避けられます。また、家族間のトラブルを回避することで、不必要に家族仲を悪くしてしまうこともなくなります。
親が健康なうちに家族信託の契約を締結する
親と子どもとの間で家族信託契約を締結する場合には、親が健康なうちに契約を締結するようにしましょう。特に、親が高齢であると、認知症が急速に悪化してしまうことはよくあることです。
親が認知症などにより単独で契約を締結できなくなると、家族信託が組めなくなってしまい、成年後見制度など他の制度に頼るしかなくなってしまいます。また、親が単独で契約を締結できる状態であったとしても、家族信託という複雑な制度の理解はできなくなってしまっているということもあります。
親が健康なうちに家族信託について話し合い、信託契約を締結するようにしましょう。
家族信託の組成やトラブル対応を依頼できる専門家
家族信託の組成について相談できる専門家は、主に弁護士や司法書士です。
大切なのは、家族信託について十分な知識を有している弁護士や司法書士に相談・依頼することです。単に弁護士や司法書士というだけでは家族信託についてよく分かっていないということもよくあるので注意が必要です。
また、家族信託に関連して実際にトラブルが発生してしまったら、そのトラブル対応を依頼できるのは弁護士だけです。弁護士は、法的トラブルへの対応の専門家であり、弁護士に依頼すればあなたの代わりに交渉や訴訟などの手続きを通じてトラブル対応をしてくれます。
いったんトラブルになってしまったら司法書士では基本的に対応できないので、弁護士と司法書士の違いをしっかりと意識した上で、トラブルについては必ず弁護士に相談・依頼しましょう。
まとめ:家族信託のトラブル対応は弁護士に相談・依頼しよう
家族信託では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
もちろん、家族信託でトラブルが発生しないように事前にしっかりとした契約書を作るなどしておくことは重要なことです。
しかし、いくら対策をしたとしても、トラブルが起こる時はあります。
家族信託のトラブル対応ができるのは弁護士だけです。家族信託でトラブルが発生したら、放置せずにすぐに弁護士に相談・依頼するようにしましょう。