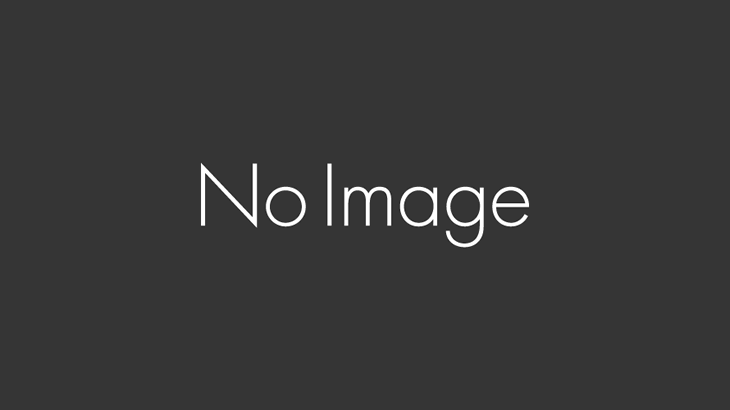「現金手渡しで生前贈与を行っておけば税務署にはばれずに税金を納めずに済むのかな?」
生前贈与を行うのであれば、納める税金は少しでも減らしたいものですよね。
たしかに、現金手渡しで生前贈与を行い、そのことが税務署に全く認識されないまま終われば、贈与税などの税金を納めることなく贈与を終えることができるかもしれません。
しかし、現金手渡しの生前贈与であれば税務署にばれないというわけではありません。現金手渡しでも生前贈与をしたことが税務署にばれるリスクは十分に高いです。
もし贈与税の申告をしないまま現金手渡しの生前贈与を続けていて、そのことが税務署にばれてしまったら、追加でペナルティとしての税金を納めなければならないなどのリスクがあります。
無申告のまま現金手渡しの生前贈与をすることは決しておすすめできません。
目次
現金手渡しの生前贈与でも税務署にばれる!
たとえ税務署にばれないようにと思っていても、「現金手渡しの生前贈与は税務署にばれる」と思っておいたほうがよいです。税務署は、たとえ現金手渡しでも贈与がなされたことを把握する手段を複数持っています。
そもそも生前贈与は現金手渡しでも許される?
そもそも、生前贈与の方法に決まりはなく、現金手渡しで生前贈与をすること自体は禁止されていることではありません。現金手渡しでの生前贈与がただちに違法となるわけでもありません。
現金手渡しの生前贈与が税務署にばれる理由
現金手渡しの生前贈与が税務署にばれる理由にはいくつかあります。
また、贈与を受けた側がもらった現金を銀行口座に預け入れた場合にも同様です。不自然な預け入れの履歴は、「誰かから現金でお金をもらったものを預け入れたのではないか?」と疑うきっかけになります。
さらに、贈与を受けた側がもらった現金で高価な買い物をしたとすれば、「そのお金の出所はどこなのか」と税務署職員に疑われて生前贈与が発覚する可能性もあります。
現金手渡しでの生前贈与の直後に贈与したことがばれるとは限らず、生前贈与をした人が亡くなったタイミングで生前贈与がばれることもあります。これは、税務署が相続税の調査の一環として、被相続人(生前贈与をした人)や相続人(生前贈与を受け取った人)の預金口座のお金の動きを調べることがあるからです。
秘密にしていた現金手渡しの生前贈与がばれたらどうなる?
秘密にしていた現金手渡しの生前贈与が税務署にばれることには、大きなリスクがあります。
追徴課税の対象となる
現金手渡しの生前贈与をしていたのに適切に贈与税の申告をしておらず、そのことが税務署にばれたら、本来の贈与税を納める義務が生じるとともに、ペナルティとして追加の税金を納めなければならないこと(追徴課税の対象となること)があります。
そもそも、本来の贈与税としては、1年間の贈与額合計を計算し、贈与税の基礎控除額である110万円を差し引いた額について、課税対象となる額に応じて10%〜55%の税率で計算し、所定の控除額を差し引いた分を納めなければなりません。
もし3,510万円の現金を手渡しで生前贈与したとすれば、納めるべき税額は、次の計算式により1,470万円となります。
- (3,510万−110万)×55%−400万円=1,470万円
参考:
贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
このような本来の税額に加えて、贈与税を脱税していたとみなされると、ペナルティとして追加の税金を課されることもあります。
無申告加算税は、税務調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合が最も軽く、本来納付すべき税金に5%を掛けた金額が無申告加算税として課せられます。一方、税務調査を受けて申告納税額の決定を受けた場合などには、本来納付すべき税金に最高30%を掛けた金額が無申告加算税として課せられます。
これだけでなく、わざと隠蔽工作をするなどして税金逃れをしていたと評価された場合には、加算税の中では最も重いペナルティである「重加算税」が課され、さらに高い税率で税を納めなければなりません。
贈与税の時効は原則6年だが悪質な場合は7年
贈与税の時効(除斥期間)は原則6年です。
もっとも、わざと税を逃れるための隠蔽工作をした場合などには、時効は7年となります。贈与税を納めないといけないことを分かっていながらわざと申告しないままでいた場合などには、このケースに該当すると判断される可能性があります。
「最長でも7年なら、贈与したことが7年間ばれなければ贈与税を納めなくても済む?」と考えてしまうかもしれません。
しかし、実際には6年(または7年)もの間にわたり税務署に贈与がばれないでいることは難しいです。
税務署は、安易に時効を成立させるようなことはしません。
贈与税には時効がありますが、時効が成立することを期待してこっそりと現金手渡しで生前贈与をしようとは考えないことが大切です。
現金手渡しで生前贈与した場合の贈与税はどれくらい?
現金手渡しで生前贈与した場合の贈与税がどれくらいになるのかについても把握しておきましょう。
年間贈与額が110万円以下のケースの贈与税
年間贈与額が110万円以下のケースでは、贈与税はゼロとなります。
ここで注意すべきなのは、贈与税は、受け取った人についてかかる税金なので、110万円という数字も受け取った総額で考えなければならないということです。
年間贈与額が110万円を超えるケースの贈与税
年間の贈与額が110万円を超えるケースでは、贈与税が発生します。
贈与税の税率には、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2つがあり、それぞれ贈与税額が異なります。
「特例贈与財産用」の税率で計算すべき場合とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(2022年3月31日以前の贈与については20歳)の者が、直系尊属(父や母、祖父母など)から贈与を受けた場合です。
「一般贈与財産用」の税率で計算すべき場合は、「特例贈与財産用」に該当しない全ての場合であり、例えば、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年であるもの、兄弟姉妹間の贈与、親族関係にない他人間の贈与などが該当します。
一般贈与財産用の税率は、次のとおりです。
- 200万円以下:10%
- 300万円以下:15%(10万円)
- 400万円以下:20%(25万円)
- 600万円以下:30%(65万円)
- 1,000万円以下:40%(125万円)
- 1,500万円以下:45%(175万円)
- 3,000万円以下:50%(250万円)
- 3,000万円超:55%(400万円)
特例贈与財産用の税率は、次のとおりです。
- 200万円以下:10%
- 400万円以下:15%(10万円)
- 600万円以下:20%(30万円)
- 1,000万円以下:30%(90万円)
- 1,500万円以下:40%(190万円)
- 3,000万円以下:45%(265万円)
- 4,500万円以下:50%(415万円)
- 4,500万円超:55%(640万円)
このように、親から成年に達している子どもに贈与するケースなどでは、原則的なケースに比べて納める贈与税額は低くなるように設定されています。
現金手渡しで生前贈与をする場合の注意点
現金手渡しで生前贈与をすること自体は何も違法なことではありませんし、現金で受け取るほうが都合の良いこともあるでしょう。決して現金手渡しで生前贈与をしてはいけないというわけではありません。
もっとも、現金手渡しで生前贈与をするのであれば、注意点を押さえて行うことが大切です。
必ず贈与契約書を作成する
現金手渡しで生前贈与をする際には、贈与契約書を作成することが重要です。
贈与契約書があれば、実際に誰から誰に対していついくらの贈与がなされたのか、客観的な記録を残すことができます。
また、作成する贈与契約書は、実際の贈与の内容のとおりに作ることが大切です。実際になされた贈与の内容とは異なる贈与契約書を作成することは、本当にあった贈与の内容を偽る行為として厳しくチェックされる可能性が高まります。
贈与契約書は、贈与の事実をはっきりとさせるために有効であり、様々なトラブルを防ぐ手段となるので、できる限り作成することがおすすめです。
贈与の都度に贈与契約書を作成する
数年のうち何回かに分けて贈与をしたのであれば、その都度贈与契約書を作成しましょう。
もしその都度贈与契約書を作成しなかったのであれば、総額をまとめて贈与したものとみなされるリスクがあります。
もし、「100万円を7年間にわたって毎年贈与する」という内容の贈与契約を締結してその旨の贈与契約書を1通だけ作成したとすると、「100万円を7年間に分けて合計700万円の贈与を受ける権利」をその贈与契約の時に得たと評価される可能性があります。
1年に110万円までの贈与であれば非課税ですが、ある年に「700万円の贈与を受ける権利」を得たと評価されてしまえば、700万円を基準として贈与税がかかってしまうリスクがあります。
贈与契約はその都度締結するようにして、贈与契約書も贈与契約ごとに作成するようにすることが不要な課税リスクを回避するために大切です。
相続開始前一定期間以内にした贈与は相続財産に加えられる
被相続人が亡くなって相続が開始してから一定期間以内に行っていた生前の贈与は、贈与の金額を相続財産に加えた上で相続税の課税対象として計算しなければなりません。
この「一定期間」とは、2023年中までの贈与については3年ですが、2024年以降は少しずつ延長され、2031年からは7年とされます。
生前の贈与であっても相続税の課税対象になるものがあるということには注意しておきましょう。相続税を節税したり調整したりしようという場合には、特に注意が必要な点です。
適切な生前贈与の方法
生前贈与を行うのであれば、適切な方法を選んで行うことが大切です。
贈与契約書を作成した上で銀行振込により贈与する
贈与契約書を作成することが重要であることはすでに述べたとおりです。
また、贈与の方法についても、できれば現金手渡しではなく銀行振込によることが望ましいです。銀行振込であれば、贈与をしたという事実がはっきりと残り、贈与の事実を隠していると税務署に疑われるリスクが減るからです。
もし何らかの事情でどうしても現金手渡しで贈与を受けるという場合には、できる限り領収書を作成し、贈与を受けたお金を銀行口座にすぐに入金するなどして、客観的に贈与があったことが分かるようにしておくことが望ましいです。このようにすることで、後に税務署から現金手渡しでの贈与について調べられた際にも、実際にいつどのような贈与があったのかをはっきりと証明することができ、不必要に脱税を疑われるリスクを減らすことができます。
110万円の贈与税の基礎控除は最大限に活用する
年間110万円までであれば、贈与をしても贈与税がかかりません。この110万円の枠を贈与税の「基礎控除」と言います。
贈与税の基礎控除の枠内に収まる贈与であれば、現金手渡しであるかどうかにかかわらず贈与税を支払う必要はありません。
ただし、最初から「300万円を贈与するが、贈与税を回避するために年100万円を3回に分けて贈与する」とはっきり約束してしまうと、「300万円の贈与を受ける権利」を一括して得たものとして課税対象となるリスクがあります。
贈与税の特例制度は積極的に活用する
贈与税の特例制度は積極的に活用しましょう。特例制度の活用により、節税対策を図ることが可能となります。
例えば、贈与税には次のような特例制度があります。
- 相続時精算課税制度
- 配偶者控除
- 住宅取得等資金の贈与の非課税特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
- 教育資金の一括贈与にかかる非課税制度
このうち、相続時精算課税制度には、2024年1月1日から年110万円までが非課税となる基礎控除が新たに設けられました。これにより、さらに節税効果を高めることができるようになりました。
生前贈与を税理士・弁護士に相談するメリット
生前贈与は、生前の相続対策に詳しい税理士や弁護士に相談することがおすすめです。
税理士・弁護士に相談するメリットには、次のようなものがあります。
- 現金手渡しでの生前贈与についてどのような方法で行えばリスクを減らせるのかアドバイスしてくれる
- どのような贈与をすればどれだけ贈与税がかかるかを計算してくれる
- 贈与税を節税するために取ることのできる手段としてどのようなものがあるのかアドバイスしてくれる
- 贈与税を納めなければならない場合には依頼すれば申告手続きを代わりに行ってくれる
- 万が一税務署から調査が入った場合にも依頼すれば対応してくれる
- 相続税の節税につながる生前の相続対策について具体的な事情に応じてアドバイスしてくれる
贈与税や相続税の制度は難しく、税に関する知識が十分になければなかなかうまく対応できないものです。
贈与税や相続税に詳しい税理士や弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けた上で望む形で生前贈与を実現することが可能となります。
生前贈与をしようと思ったら、まずは相続対策に詳しい税理士や弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ:無申告での現金手渡しの生前贈与はばれる!適切な方法で生前贈与を
無申告での現金手渡しの生前贈与は、隠そうと思って行っても最終的には税務署にばれると思っておいたほうがよいです。
現金手渡しの生前贈与そのものは違法ではありませんが、適切に申告をしなければ脱税となってしまい、追加で課税されるなどのリスクがあります。
生前贈与は、適切な方法で行うことが重要です。
生前贈与をしようと思ったら、まずは相続対策に詳しい税理士や弁護士に相談してみるようにしましょう。あなたの事情に合った適切な生前贈与のしかたをアドバイスしてくれます。
税理士や弁護士に相談した上で、安心して望む形での生前贈与を実現しましょう。