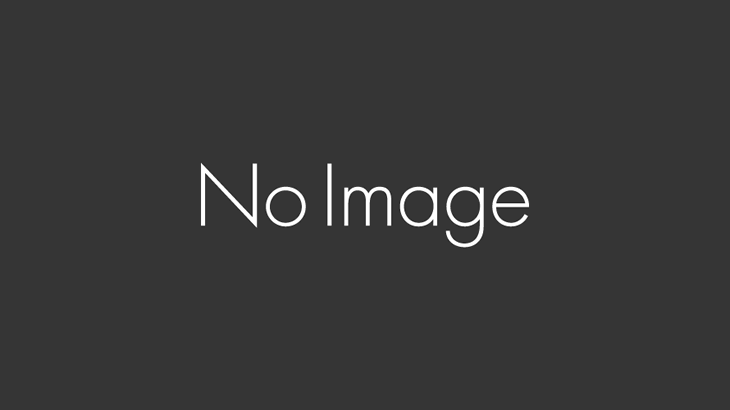「相続登記をしなければならないけれど、費用を節約したい。安く済ませられる方法はあるのかな?」
相続登記の費用を節約したい場合には、いくつか方法があります。もっとも基本的な方法としては、専門家報酬をなくすことです。しかし、専門家に依頼せずに自分で相続登記を行うことにはデメリットもあり、注意が必要です。
目次
相続登記とは?必ずしなければならない?
そもそも相続登記とはどのようなものなのでしょうか。このことについてご説明します。
相続登記とは
相続登記は、不動産の登記を管理している法務局という役所に必要書類を提出することで手続を行います。
相続登記が完了することで、相続で得た不動産について完全な所有権を取得することができます。
相続登記は義務!必ずしなければならない
相続や遺言によって不動産を得た相続人は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。また、遺産分割が成立した場合についても、不動産を得た相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
さらに、2024年4月1日より前に相続が開始している場合にも、3年間の猶予期間のうちに相続登記をしなければなりません。
相続登記の申請は遅れずに行うようにしましょう。
相続登記にかかる費用には何がある?
相続登記は無料でできるわけではなく、一定の費用がかかります。
相続登記にかかる費用には、次のようなものがあります。
- 申請に必要な書類の取得費用
- 登録免許税
- 専門家に依頼する際の報酬
それぞれの費用は、相続ごとの事情に応じて変わってくるため、一律に「この額」と言うことはできません。個別の相続ごとに費用は変わるということを前提にしたおおまかな目安については次のとおりです。
申請に必要な書類の取得費用
相続登記を申請するには、「誰がいつ亡くなったか」「相続人は誰か」「相続する不動産の価値はどれくらいか」などが分かる書類を添えなければなりません。
具体的には、次のような書類を準備します。それぞれの書類は居住地または本籍地の市区町村の役所などで取得することができます。書類の取得には費用がかかり、1通あたりの取得費用の目安は次のとおりです(自治体ごとに料金が変わることがあります)。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 改正原戸籍謄本:750円
- 住民票の除票の写し:300円程度
- 住民票の写し:300円程度
- 戸籍の附票の写し:300円
- 印鑑登録証明書:300円程度
- 固定資産評価証明書:200〜400円程度 など
例えば、被相続人に関する戸籍謄本については、被相続人が出生してから死亡するまでの経過が記載された全ての戸籍謄本を集める必要があります。このため、複数通の戸籍謄本が必要になることも少なくありません。
また、書類を郵送で取り寄せる場合には郵送料金も必要になります。
個別の事情に応じて必要な金額は変わりますが、これらの必要書類を集めるためには合計で数千円から1万円程度がかかると思っておけばよいでしょう。
登録免許税
必要となる登録免許税の額は、次の計算式によって算出した金額です。
例えば、相続登記を申請する不動産の固定資産税評価額が1,500万円であれば、登録免許税の額は6万円となります。
専門家に依頼する際の報酬
相続登記は司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで代わりに手続を行ってもらうことができます。
司法書士や弁護士に依頼した場合には、手続の報酬としてのお金を支払わなければなりません。
このような専門家への報酬は具体的にいくらと統一されているわけではなく、専門家ごとに異なる報酬額が設定されています。一般的には、相続登記が1件の場合は概ね5万円〜10万円程度が一つの相場です。
相続登記の費用を節約する方法
相続登記の費用を節約する方法の基本は、「自分で相続登記の手続をする」ことです。このことも含めて、相続登記の費用を節約する方法についてご説明します。
自分で相続登記の手続をする
相続登記の手続を専門家に依頼せずに自分で行えば、専門家に依頼するのに必要な報酬の分だけ相続登記にかかる費用を節約することができます。
相続登記の手続は、主に次のような流れで行います。
2. 相続登記の手続に必要な書類を集める
3. 遺産分割協議書を作成する(相続人同士の間で遺産分割協議をする場合)
4. 相続登記申請書を作成する
5. 管轄のある法務局に相続登記の申請をする
6. 法務局から指示があれば、補正や訂正の指示などに対応する
7. 相続登記が無事に完了したことを確認する
これらの手続を全て自分で行うことさえできれば、専門家に報酬を支払わなくても相続登記を済ませることができるため、専門家報酬の分を節約することができます。相続登記にかかる費用の大部分は専門家に支払う報酬であるため、専門家に依頼せずに自分で相続登記を完了できれば相続登記にかかる費用の大部分を節約できるということになります。
相続登記に必要なそれぞれの手続について具体的にどのようにすればよいのかは、インターネットや書籍で調べるほか、法務局に確認することでも調べることができます。法律の理解や書類仕事が得意な人であれば、全て自分で相続登記を済ませるという人も一定数います。
場合によっては、手続の詳細な流れや分からない部分だけは専門家に相談するなど、柔軟な対応が必要になることもあります。
自分で取得できる書類は自分で取得する
自分で取得できる書類は自分で取得しておくことで、専門家に依頼したとしても費用を減らせる可能性があります。
例えば、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は、相続登記だけでなく亡くなった方の預貯金の引き出しなどの際にも必要となるため、相続登記の際にはすでに手元にあるということもあります。
これらの書類を相続登記の際にも使うことで、書類を集めるために必要な費用を節約できることがあります。節約できるのは数千円〜1万円程度ですが、書類を二重に集める無駄をなくすことができるので、合理的です。
登録免許税の免税制度を利用する
相続登記の申請の際に納めなければならない登録免許税は、所定の条件を満たすことで免除してもらうことができます。この制度を利用することで、場合によっては、数万円程度かかる登録免許税を節約することができます。
登録免許税の免税制度には次のようなものがあります。
- 相続によって土地を取得した人が相続登記を済ませないまま亡くなった場合
- 不動産の価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合
例えば、祖父が土地を所有していたが亡くなり、それを受け継いだ父が土地について相続登記をしないままさらに亡くなって子が土地を受け継ぐ場合を考えてみましょう。
このような場合、土地を受け継いだ子が相続登記を申請するにあたっては、本来祖父から父への相続登記と父から子への相続登記の2つを行わなければなりません。
これに伴い、登録免許税も2回分納めなければならないかのようにも思えます。しかし、この免税制度の適用を受けることで、祖父から父への相続登記の分については登録免許税を納めなくて済み、父から子への相続登記の分についてのみ登録免許税を納めればよいことになります。
オンライン申請を活用する
相続登記の申請は、法務局の窓口に紙の書類を提出して行うだけでなく、オンラインで行うという方法もあります。オンラインで相続登記を行えば、法務局まで直接行くための交通費を節約できることがあります。
例えば、東京に住んでいる相続人が、被相続人が京都に所有していた不動産について相続登記を行おうとした場合には、東京から京都へと直接出向いて管轄のある京都の法務局の窓口で相続登記を申請しなければなりません。
このために新幹線で移動するのであれば、東京から京都へと移動するための往復の新幹線代として数万円を負担しなければなりません。数万円の交通費は、相続登記を専門家に依頼するケースと比べても、かなり大きな負担であると言えます。
さらにそのほかの地方にも被相続人が不動産を所有していれば、その不動産の数だけ交通費の負担が増えることにもなります。
オンライン申請をするのであれば、このような交通費を節約できます。
オンライン申請をするためには、専用のソフトウェアを導入したパソコンが必要になります。また、一部の書類については別途郵送する必要があります。完全にオンラインだけで手続が終わるわけではないことには注意が必要です。
他の相続人と相続登記の費用分担について話し合う
他の相続人と相続登記の費用分担について話し合うことで、ご自身が負担しなければならない相続登記費用の一部を他の相続人との間で分担してもらえる可能性があります。
例えば、次のようなケースでは、他の相続人に費用の分担を相談できるかもしれません。
- 価値のない原野などで他の相続人が誰も引き受けようとしなかった不動産について、話し合いの上で自分が引き受けて相続するケース
- 一緒に住む家族である複数の相続人を代表して、自分の名義で相続登記をするケース
これらのケースは、不動産を相続して相続登記の名義人となる人以外の相続人にも利益があるケースです。このように他の相続人にも利益があるのに、自分ひとりが相続登記をするというようなケースでは、相続登記の費用を分担してもらうように相談することで応じてもらえる可能性があります。
このほかに、相続人全員の合意さえあれば、被相続人の遺産の中から相続登記にかかる費用を出すこともできます。例えば、被相続人が預金と土地を遺して亡くなった場合には、相続人全員の合意の上で遺産である預金から相続登記の費用を出すことができます。
相続登記の費用を節約できる可能性がある人
相続登記の費用節約は誰にでもできることではありません。相続登記の費用を節約できる可能性がある人とは、主に次のような人です。
- 相続人がひとつの家族であるなど家庭構成として一般的であり、法定相続人の数も2〜3人程度と多すぎない人
- これまでの相続人がしっかりと相続登記を終えており、自分の相続登記だけを行えばよい人
- 申請する不動産の数が少ない人
- 平日の日中であっても空いており、時間に余裕があって難しい手続でも調べて自分で進めていける人
このような人であれば、相続登記の手続が比較的簡単であるため、専門家に依頼せずに自分だけで相続登記を終えられる可能性があります。
これに対して、次のような人は相続登記を自分だけで終えることは難しく、費用をかけて司法書士や弁護士といった専門家に相続登記を依頼する必要があることが一般的です。
- 被相続人の血縁関係が複雑であったり一般的ではなかったり、法定相続人の数が多数にのぼる人
- これまで何代にもわたって相続登記が行われないまま放置されており、過去の分の相続登記についても処理しなければならない人
- 相続登記を申請する不動産の数が多かったり、各地方に不動産が散らばっていたりする人
- 平日の日中が仕事などで忙しく、時間に余裕がない人
- 難しい書類の手続を自分だけでこなす自信がない人
費用を節約するために相続登記を自分で行うデメリット
相続登記の費用を節約するためには相続登記を自分で行うのが最も一般的な方法ですが、費用を節約するために相続登記を自分で行うことには次のようなデメリットもあります。
- 相続登記の手続がうまくいかずに失敗してしまう可能性がある
- 手続のためにたくさんの手間や時間がかかってしまい負担が大きい
- うまく手続が進まなければ心理的な負担を抱え続けたままになってしまう
- 手続がうまく進まずに相続登記を放置してしまって相続登記義務に違反する可能性がある
- 結局途中から専門家に依頼することとなり、かけた労力が無駄になるおそれがある
相続登記の申請のために揃えなければならない書類は厳密に決まっており、個別の事情に応じて少しずつ異なります。自分のケースではどのような書類が必要なのかを自分で判断して的確に書類を揃えることは簡単なことではありません。また、間違えた申請をしてしまうと登記が行えず、何度も補正や訂正をしなければならない可能性もあります。
相続登記の手続を全て自分だけで行うことは決して簡単なことではなく、むしろ自分だけでできる人のほうが少ないと言っても言い過ぎではありません。少しでも「自分だけではできないかもしれない」と思ったら、放置せずになるべく早く専門家に依頼するようにしましょう。
相続登記を専門家に依頼するメリット
相続登記を依頼できる専門家は、次の2つに限られます。
- 司法書士
- 弁護士
司法書士は登記の専門家であり、相続登記についても取り扱っています。弁護士は、法律事務全般の専門家であり、相続登記についても代わりに行うことができます。
この2つ以外の資格を持つ人や無資格の人は、相続登記の手続を代行することができません。この2つ以外の資格を持つ人や無資格の人に相続登記の手続を相談したり任せたりしないように注意しましょう。
相続登記を専門家に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
- 専門家が代わりに基本的に全ての手続を行ってくれるので、自分で相続登記の手続のために何か対応しなければならないという負担が大幅に軽減される
- 自分で相続登記の手続について調べたり書類を集めたりする負担がなくなる
- 専門家が正確に手続を進めてくれるので、手続のミスで相続登記が遅れたり受け付けられなかったりするリスクがなくなる
- 相続登記に関連して、依頼すればその他の相続に関する悩み事についても相談に乗ってもらえてまとめて相続に関する手続やトラブルを解決できる
相続登記を専門家に依頼するメリットには、このように様々なものがあります。これらのメリットを受けられることは、特に被相続人が亡くなって慌ただしい時期の相続人にとっては非常に大きな意味があると言えるでしょう。
これに対して、専門家に依頼する唯一のデメリットは、専門家への報酬を支払わなければならないということだけです。しかし、専門家への報酬を支払っても依頼する価値はあると言えます。
まとめ:相続登記を自分ですれば費用を節約できるがデメリットもある
相続登記費用を節約する一番の方法は、「自分で相続登記をする」ということです。
しかし、自分で相続登記をすることには様々なデメリットもあり、簡単にはおすすめできません。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼することで、手間や負担なく速やかに相続登記を完了することができ、「結局はこちらのほうが良かった」という結果になることも多いです。
自分で相続登記をしようと試みてみて、少しでも「自分だけでは手続を完了できない」「難しくて手続が分からない」「やっぱり自分で相続登記の手続をするのはやめたい」と思ったら、放置せずにすぐに専門家に相談・依頼するようにしましょう。